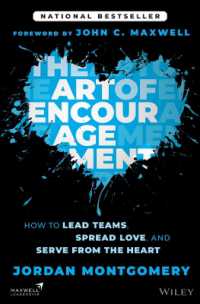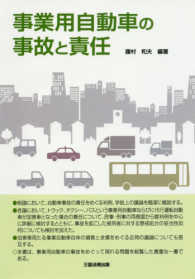内容説明
江戸時代の塵捨場、明治維新とリサイクル、近代的な焼却施設の設置、ごみ収集のはじまりから定着へのドラマ、そして今後への課題―知られざる京の一面がここにある。
目次
1 京都1200年の歴史とごみ問題
2 江戸時代の京都のごみ処理
3 洛中塵捨場
4 明治維新と京都のごみ処理
5 化芥所―ごみ再資源化の試み
6 京都市の成立とごみ問題
7 汚物掃除法の成立
8 ごみ全量焼却への取り組み
9 近代的なごみ焼却炉の建設
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
chang_ume
8
非常に面白かった。循環型社会の理想(幻想?)が投影されがちな近世社会に関して、京都洛中の「ゴミ処理」をめぐる都市問題が描き出される。奉行所からの再三にわたる禁令の傍で、鴨川・堀川・西洞院川といった都市河川にせっせとゴミ投棄を続ける京都住民。「川筋を塵捨場のように心得え候ものもこれ有る趣にて」と町触の本文中で嘆く奉行所。一方で問題を通して、塵捨場として再活用される惣構(御土居)や寺社境内さらには聚楽第遺構(天秤堀)など、近世都市社会における地域資源のトポスも浮かび上がります。ゴミから見た京都史。良書でした。2018/12/27
アメヲトコ
7
99年刊。江戸のゴミ処理については割と色々書かれているものの、京都はどうだったのだろうと思って調べていたら本書に辿り着きました。近世には川という川、溝という溝に人々がゴミを捨てまくっていて割と無法地帯だった一方で、近代になるとゴミの再資源化とか全量焼却とか廃棄物場での温熱利用とか、かなり最先端なことを他都市に先駆けてやっているのが面白い。著者は当時京都府の職員で、産業廃棄物行政に携わった経験から古文書を独学してこうして一冊をまとめたとのこと。頭が下がります。2021/01/03