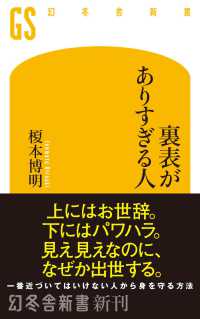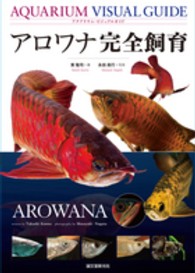内容説明
オホーツク海で蟹をとり、缶詰をつくる蟹工船。そこで働く者たちは、情け知らずな監督のもとで、死者がでるほど過酷な労働を強いられていた。
著者等紹介
渡邉文幸[ワタナベフミユキ]
1948年静岡市生まれ。早大文学部卒業、東大新聞研究所研究生を経て、74年に共同通信社入社。2004~10年法務省広報企画アドバイザー、元・理論社編集顧問、現在、日本BS放送報道局顧問(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nakanaka
57
言わずと知れた名作。ようやく読めました。劣悪な環境での作業を強いられる労働者とそれを強いる管理者の話。事実に基づいた話であることに衝撃を受けるとともに、法の外のこととしてそれを許していた国に怒りを覚えます。人権が無視された時代ということでしょうか。後世に残すべき作品であることは間違いありませんね。かといって、この作品や出来事を理由として資本主義が全くダメであると言ってしまうのは違う気もします。プロレタリア文学について興味が湧いてきました。また、労働者の東北訛りが心地良かったです。2025/04/22
あじ
49
【現代語訳にて読む】物語は船乗りたちの過酷な労働現場を告発する、訴状の様相を呈する。虫けらのごとく労働者を扱う船長を討伐しようと、一致団結する漁夫たち。しかし憎むべき相手は船長ではなく、資本家(雇い主)なのだと思い知らされる。そのやりきれなさは同プロレタリア文学の葉山嘉樹『海に生くる人々』と重なった。窮屈な船に押し込められた漁夫たちの無念さが、船と一緒に沈んでいくようで暗澹とした気持ちになる。また海を生き物のように大胆に捉えた多喜二の技巧は、船酔いと心酔が同時に襲ってくる程の衝撃を含んでいた。2017/01/11
Nao023
45
今も過酷な労働は、カタチを変えて続いている。今や団結することすら出来ない環境になっている。 声を上げるか、ゲームから降りるか、である。2025/06/13
黒猫
23
プロレタリア文学の最高峰と言われる小林多喜二の蟹工船。現代語訳でスラスラ読める。かなり忘れていたが思い出した。国家権力→財閥の癒着。財閥→労働階級への無慈悲極まりない理不尽な搾取の構図を、蟹を取る船の小さな場所を舞台にあぶり出しているのは見事。下位には下位で差別があり、上位には上位の差別があり、細々とした格差が社会に蔓延していることを小林多喜二は見逃さない。凄まじい洞察力。それ故に特高警察にマークされ非業の死を遂げた。現在でもこの搾取の構図はあまり変わらない。小林多喜二は今をも見据えていたのだろうか。2018/06/10
のんxxx
22
プロレタリア文学とは何ぞや、という状態の私でしたが、ようやく解説を読んで理解できました。ちょっと前に流行ったよね、この本。と思っていたら流行ったのは2008年ですって。結構前じゃないですか。派遣社員や契約社員が低賃金で過酷な労働をしていた時代とのこと。ちなみにこの本は読みやすく訳された本。でもなかなかに悲惨な描写が多くてちょっと鬱気味になります。原文はどうなんなんでしょう。ちょっと気になるけど、しばらくはいいかな‥。2024/03/16
-
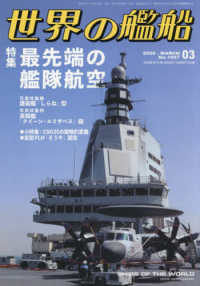
- 和雑誌
- 世界の艦船 (2026年3月号)
-

- 電子書籍
- 魔王アプリでS級ハンターになれました【…