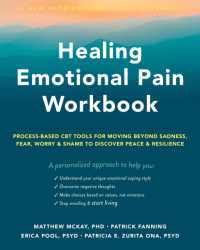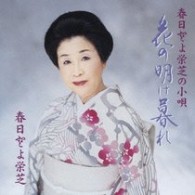内容説明
ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬまばあさん。ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬまばあさん。いつもいねむりぬまのそこ。こどもがくるとでてくるぞ。つかまえられたらさあたいへん。おおきなおなべでぐつぐつぐつ…。みんなが知っている遊び歌。「ぬまばあさんのうた」を知っていますか。
著者等紹介
岡田淳[オカダジュン]
1947年兵庫県に生まれる。神戸大学教育学部美術科を卒業、西宮市内で教師をつとめる。1981年『放課後の時間割』で日本児童文学者協会新人賞。1984年『雨やどりはすべり台の下で』で産経児童出版文化賞。1987年『学校ウサギをつかまえろ』で日本児童文学者協会賞。1988年『扉のむこうの物語』で赤い鳥文学賞。1991年『星モグラサンジの伝説』でサンケイ児童出版文化賞推薦。1995年「こそあどの森の物語」1~3の三作品で野間児童文芸賞。1998年「こそあどの森の物語」1~3の三作品が国際アンデルセン賞オナーリストに選定される(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
64
シリーズ8冊目。湖に出現する水路。ヨットでたどりつく三人組(もちろんスキッパーとふたご)が、「ぬまばあさん」を恐れながらも、本当の思いを知って、望みをかなえることに。住人の少ないこそあどの森に、そういう伝説があったこと、水の精の大きな魚に、森の過ごしてきた時間の層の厚さを感じる。冒頭のバーバさんの手紙がどのように生かされるのかと思ったら……でした。2019/07/19
カール
24
こそあどの森にすむ人たちの始めのエピソード。ばらばらのようなのに、最後に繋がっていく構成は読んでいてお見事。初めは怖いお話なのかなと思っていたら、ぬまばあさんにあんな悲しい過去があったなんて。人は自然と繋がっているし、生かされているんですね。2017/07/24
るんるん
23
湖や土地に名前に、過去の息づかいが聞こえる。昔、誰かがつけた呼び名は今も受け継がれ、声となり音となり、あらゆる命は生まれ変わる。「いただきます」あらためていい言葉だな、と思う。2017/11/03
くぅ
22
こそあどの森、巻が進むたびに神話感が増してきて面白い。今作も双子に巻き込まれ、ぬまばあさんに捕まり煮て食べられる話かと思いきや…。ちゃんと最初のバーバさんからの手紙が効いてる。考えてみたら一番哀しく恐ろしい思いをしながら耐えていたのは"ぬまばあさん"だったというね。そして、ぬまばあさんのうた、病みつきになる。是非双子にフシをつけて歌ってほしい!2021/09/20
七月せら
19
真っ赤な宝石のように空を彩る夕焼けの色がまぶたの裏いっぱい。年に幾度とない見事な夕焼けは胸躍る冒険の予感であり、穏やかな日常の一幕でもある。スキッパーや双子たちのした不思議な探検の1日と大人たちのまったり釣り日和の1日がゆるやかに重なって奏でるハーモニーは、遠い昔から人びとに寄り添ってきたこそあどの森だから「きく」ことができるのだと思います。2020/06/25