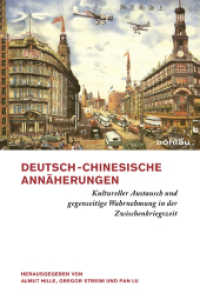内容説明
日本古代において、本来中国語を書き表す文字が、どのように日本語を記述しえたのか。漢字の受容と伝来をはじめ、上代の文字法や万葉仮名・人麻呂歌集などの文字資料を考察し、古代日本語の姿を浮かび上がらせる。
目次
第1章 漢字の伝来と受容(漢字の受容;鉄剣銘・木簡;古代東アジアにおける漢文の変容;漢文の受容と訓読)
第2章 上代文献の文字法(上代の文字法;上代文献における「所」字;上代文献における「有・在」字;上代文献における否定の用字)
第3章 万葉仮名論(万葉仮名;訓仮名の成立;『上宮聖徳法王帝説』の万葉仮名;言語資料としての歌経標式)
第4章 人麻呂歌集の表記(人麻呂歌集略体歌の表記の特性;人麻呂歌集とその後の上代表記;子音韻尾の音仮名について)
第5章 日本古代の地名表記(『出雲国風土記』の音韻と表記;『播磨国風土記』の音韻と表記;古代の地名表記―上代撰述風土記を中心に)
著者等紹介
沖森卓也[オキモリタクヤ]
1952年三重県に生まれる。1977年東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。現在、立教大学文学部教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
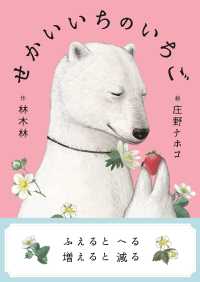
- 和書
- せかいいちのいちご
-

- 電子書籍
- めだかボックス モノクロ版 12 ジャ…