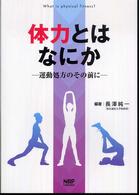出版社内容情報
執権北条泰時らが編纂した鎌倉幕府の基本法典「御成敗式目」。1232年に施行されたこの最初の武家法典を、制定過程や目的、研究史などから全体像をとらえ直す。51箇条より主要条文を選び、分かりやすく解説を加えて式目が実際にどう実践されたのかを読み解く。法の視座から当時の権力・訴訟・犯罪などの実態に迫る。巻末に現代語訳を付す。
内容説明
執権北条泰時らが編纂した鎌倉幕府の基本法典「御成敗式目」を分かりやすく解説した。制定過程や目的、研究史などから全体像をとらえ、五十一箇条より主要条文を読み解き、その全貌に迫る。巻末に現代語訳を付す。
目次
総論 御成敗式目とは何か(御成敗式目の制定過程とその目的;御成敗式目と鎌倉幕府法の構造;御成敗式目の受容史)
第1部 御成敗式目から見る権力のかたち―幕府・権門・御家人(守護と地頭―鎌倉幕府と荘園公領制;権門と法園―幕府「裁判管轄」の意図と現実;不易法―政治と訴訟との関わりから)
第2部 中世の人びとは何を争ったのか―犯罪と財産相続(罪と罰;悔返と未処分)
第3部 どのように裁判を行ったのか―裁判手続と文書(召文違背の咎―幕府裁判と社会との接点を読み解く;問状と裁判手続)
附録 「御成敗式目」現代語訳
著者等紹介
神野潔[ジンノキヨシ]
1976年、神奈川県に生まれる。現在、東京理科大学教養教育研究院教授
佐藤雄基[サトウユウキ]
1981年、神奈川県に生まれる。現在、立教大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白隠禅師ファン
春風
Ohe Hiroyuki
四不人