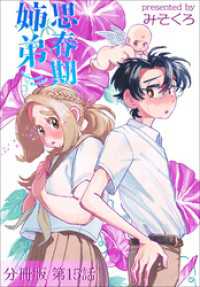出版社内容情報
日本の皇族の一員でありながら、これまで十分に知られることのなかった「王」。平将門の乱を扇動した興世(おきよ)王、源平合戦を引き起こした以仁(もちひと)王、天皇に成り損ねた忠成王など、有名・無名のさまざまな「王」たちの事績を、逸話も織り交ぜて紹介。影が薄い彼らに光を当て、日本史上に位置づける。皇族の周縁部から皇室制度史の全体像に迫る初めての書。
内容説明
日本の皇族の一員でありながら、これまで十分に知られることのなかった「王」。興世王、以仁王、忠成王など有名・無名のさまざまな「王」たちを、逸話も交えて紹介。皇族の周縁部から皇室制度史の全体像に初めて迫る。
目次
総論―皇族制度史上の王
第1章 奈良時代と平安時代前期の王
第2章 貴種性を喪失した平安時代中期の王
第3章 平安後期(院政期)の王と、擬制的な王の集団「王氏」
第4章 平安時代末期以降の天皇から分岐した皇族の王
総括―日本史上における王の存在意義
著者等紹介
赤坂恒明[アカサカツネアキ]
1968年、千葉県野田市に生まれる。2009年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程史学科(東洋史専攻)単位取得退学。早稲田大学非常勤講師などを経て、現在、内モンゴル大学モンゴル歴史学系特聘研究員(教授)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
魚京童!
17
王。よくわからん。ってか今、住民票あるんだから、グーグルに突っ込んで先祖一覧作れるよね。なんでやらないのかな。これまでは市町村単位で管理してたけど、全国的に人間の動きとかその他もろもろを可視化することができると思うし、ビッグデータとして面白いと思うんだけど、明らかにしてはならないことが日本には多すぎてダメなのかな。皇族はヒトですらないから何してもいいんだよね。羨望と侮蔑。難しいよね。皇族に人権ないらしいし。殿上人と捉えるかどうかっていう区別は大事だよね。差別にもつながるし、区別されてるのがどうかって話だし2020/03/22
さとうしん
13
倉本一宏『公家源氏』と補い合う内容で、こちらは主に賜姓されない王を扱う。系統不明とされてきた興世王の系統の推測、伊勢奉幣の使王代の河越家が擬製的に王を作名し、王氏への改姓を願い出たという話が面白い。源氏と同じく天皇の孫あたりから露骨に没落していくさまが描かれているが、中国の各王朝の皇族でももう少し扱いが丁寧なのではないかと思ってしまう。2020/01/01
六点
9
なんだか、最近「日本史史料研究会」の回し者になったかのように同会がクレジットされた本を読んでいる気がする。質が高いからしょうがないのです。それはそうと最近喧しい「皇族の身分」についての通史である。古代から近現代まで日本史上に数多の「○○王」が存在したわけであるが、それらの正体については、殆ど解明が進んでいない。世襲親王家とは違い、史料が残存していないから仕方がないのだが、史料の影から現れる「○○王」達の姿は著者の優れた筆法もあり大変魅力的である。「豚の肩ロースのうた」は実に訳が洒脱で良いですよ。2020/03/08
KOKO.H
4
親切丁寧な本。人名や用語等にはルビと解説がついているので、国史大辞典もWikipediaも不要。中断することなく読書が進み、理解も進む。小説ではないのに各「王」の個性が際立つ。「王」に関心を持つきっかけが大河ドラマ中の「興世王」であったという著者のエピソードも一興。2020/01/27
鈴木貴博
3
歴史上の「王」について、時代の流れに伴う制度や位置付けの変遷と、その中における具体的な「王」たちの諸相。2021/03/07