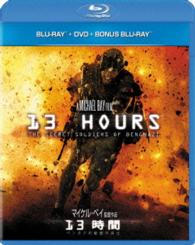出版社内容情報
明治のはじめ、荷車の技術的変革は、物流を急速に発達させ、東京の経済発展に大きく貢献した。また、人力輸送の補助力として不可欠だった「立ちん坊」とはどのような人たちだったのか。車輌の製造や管理、道路の整備や日清戦争下の輸送、立ちん坊の生活や賃金など、さまざまな視点から明治社会を掘り起こし、現代にも通じる物流問題の実態に迫る。
内容説明
明治のはじめ、荷車の技術的変革は東京の経済発展に大きく貢献した。人力輸送の補助力として不可欠な「立ちん坊」とはどのような人たちだったのか。運輸や労働の視点から明治社会を掘り起こし、物流問題の実態に迫る。
目次
序章 荷車曳きのかけ声
第1章 近代への胎動
第2章 「くるま」規則の近代化―制度改革
第3章 明治の「くるま」メカ―技術改革
第4章 都心商業地と小運送
第5章 路傍の「立ちん坊」
第6章 軍隊と荷車
第7章 東京近郊の荷車と立ちん坊
終章 近代都市と物流―経済圏の拡大と動力
著者等紹介
武田尚子[タケダナオコ]
お茶の水女子大学文教育学部卒業。2000年、東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程修了、博士(社会学)。現在、早稲田大学人間科学学術院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
-
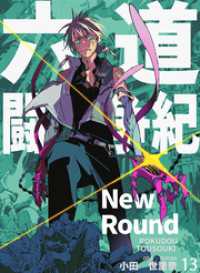
- 電子書籍
- 六道闘争紀-New Round-【単話…
-
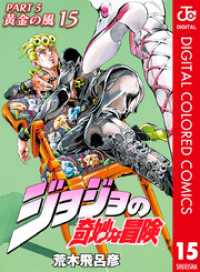
- 電子書籍
- ジョジョの奇妙な冒険 第5部 黄金の風…