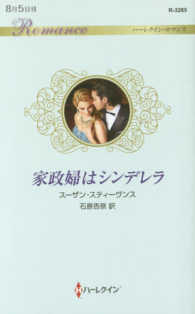出版社内容情報
近代日本における対外戦争の戦没者を主な祭神とする靖国神社。誰が祀られ、誰が祀られなかったか。揺れ動く合祀基準のゆくえを追う。
内容説明
近代日本における対外戦争の戦没者を主な祭神とする靖国神社だが、その全員は祀られていない。誰を祭神として祀り、誰を祀らないのかは時代により揺れ動く。国家補償とのズレにも触れつつ、合祀基準の変遷を追う。
目次
1 近代日本における戦没者の合祀―明治初年からアジア太平洋戦争の終了まで(東京招魂社から靖国神社へ;日清戦争から日露戦後へ;第一次世界大戦から満洲事変へ;日中全面戦争から敗戦まで―総動員体制)
2 第二次世界大戦後の戦没者の合祀(敗戦直後の合祀問題;講和独立後の大量合祀)
著者等紹介
赤澤史朗[アカザワシロウ]
1948年東京都に生まれる。1981年早稲田大学大学院文学研究科史学専攻博士課程単位取得退学。1992年立命館大学法学部教授。2013年退職。現在、立命館大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
那由田 忠
16
これは靖国の合祀者がどんな「戦死」なのかを細かく分析したもの。要は、天皇制国家の復活に賭けた志士から、明治政府への様々な反乱、外国への様々な出兵から日清戦争等々の国家の戦争に貢献した軍人や軍属、関係者をどこまで「戦死」扱いして合祀するかが揺れ動いた経緯を詳細に示す。外国に出て行くと様々な事故や襲撃、病気にあうので、どこまで補償対象にするかなど難しい判断が無数に問われることがわかる。大戦後の日本がそうした問題を一切払拭してしまったこと、これが平和国家へ大転換したあり方だということがよくわかった。2020/09/25
-
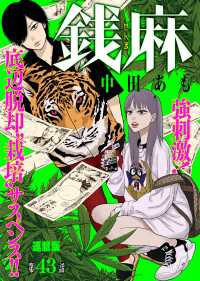
- 電子書籍
- 銭麻 連載版 第43話 うっとーしい…
-

- 電子書籍
- こどもホスピタル 分冊版(10)