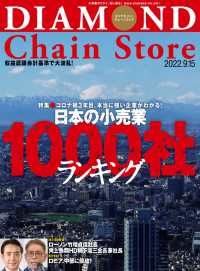内容説明
戦後、人類学・民俗学・考古学などの学会が結成した“九学会連合”。宮本常一らの共同調査から、対馬をめぐる日韓の軋轢や、「日本人」の証明を求めた奄美の人びとの姿を辿り、フィールドワークを戦後史に位置づける。
目次
序章 フィールドワークの時代(九学会連合と宮本常一の戦後;九学会連合と共同調査の展開)
第1章 対馬調査と朝鮮戦争(九学会連合と対馬調査;宮本常一が見た朝鮮戦争;対馬は日本である;「寄りし」と九学会連合)
第2章 能登調査と「調査地被害」(「島」から「半島」へ;調査団が見た能登/能登から見た調査団;古文書収集と「調査地被害」)
第3章 奄美調査と「本土」復帰(奄美群島の返還と九学会連合;奄美復帰運動とSIRIプロジェクト;沖縄と「本土」の狭間で;奄美調査と「奄美学」)
終章 九学会連合のその後
著者等紹介
坂野徹[サカノトオル]
1961年、東京都に生まれる。1985年、九州大学理学部生物学科卒業。1990年、東京大学大学院理学系研究科(科学史・科学基礎論)博士課程単位取得退学。博士(学術)。現在、日本大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
20
戦後混乱期の農業指導の日々の中、日本の輪郭を再定義するため辺境での共同研究に参加した宮本常一。しぜんに、村人の水産庁への陳情を助けたり郷土芸能の復興を助けたり、調査される側の変貌に自ら関わりそれを記録する姿勢となる。あれ?これって、社会学の、参与観察からもう一歩踏み込む「アクションリサーチ」そのものやんねえ。対象との距離をとることだけが学問じゃない。◇それぞれがまだ「学」として固まる前だからこそ成立した共同研究。その後の沈滞の時期が過ぎて、今、もういちど有効性が高まっているのでは?面倒くささは価値だよね。2014/06/01
midnightbluesky
6
はたして宮本常一という人物が浮かび上がってくるような朝鮮戦争の砲弾音のエピソードは、事実がすべての学問に一石を投じるイージーさであり、事実こそすべということがばからしくすら思えてきてしまう。2013/04/16
Sanchai
5
記念すべき読書メーター通算1000冊目の本。「戦後史」と付いている割には九学会連合調査も序盤の対馬、能登、奄美について詳述しているのみで、その後についてはさらっとしか触れられていない。国内に辺境が少なくなってきたのと、高度成長期を経て、お金を払って何でも買えるようになってきたので、地域ごとの特徴というのが薄れていったのだろうな。九学会連合調査についての記述は他でも読んでいたが、同じ時期に起きていた朝鮮戦争などと関連付けて述べられた本は初めてで、その点では目新しさがあった。2014/06/08
メルセ・ひすい
5
「九学会連合」(日本人類学会・日本民族学協会・民間伝承の会⇒日本民俗学会・日本社会学会日本考古学会・日本言語学会・日本地理学会・日本宗教学会・日本心理学会)による日本各地での共同調査(対馬2回、能登1回、金沢2回、奄美2回、現地関係者からのインタビュー)は、いかなる成果をもたらしたのか。宮本常一らの活動から、GHQ統治下の対馬、本土復帰直後の奄美の人びとの姿を辿り、フィールドワークを戦後史に位置づける。★対馬調査と朝鮮戦争 能登調査と「調査地被害」 奄美調査と「本土」復帰 九学会連合のその後 。2013/02/26
ELECTRICcommodo
2
「調査いう行為につきまとう、『誰』が『何のために』行うのかという問題」 今まで考えもしなかった。2013/04/06