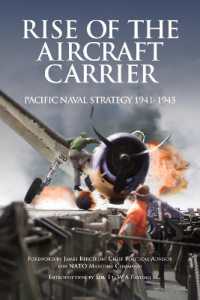内容説明
明治の政治結社から護憲政党の活躍、戦時下の政党消滅、自民党・社会党を柱とした五五年体制と派閥政治、二〇〇九年の政権交代までの政党史を平易に解説。民主政の柱、権力装置としての“政党”の実態と本質を問い直す。
目次
はじめに―政党史研究の意義
1 明治前半期における政党の誕生(‐1890年)
2 大日本帝国憲法下での政党の発展(一八九〇‐一九三二年)
3 政党政治の凋落と再生(一九三二‐五五年)
4 「五五年体制」の変貌と危機(一九五五‐八六年)
5 政治改革と政界再編(一九八六‐二〇〇九年)
著者等紹介
季武嘉也[スエタケヨシヤ]
1954年東京都生まれ。1979年東京大学文学部国史学科卒業。1985年東京大学大学院博士課程単位取得退学。現在、創価大学文学部教授、博士(文学)
武田知己[タケダトモキ]
1970年福島県生まれ。1994年上智大学文学部英文科卒業。1998年東京都立大学社会科学研究科博士課程退学。現在、大東文化大学法学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。