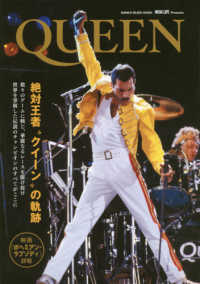出版社内容情報
おかげさまで3刷出来!
主な書評
日刊ゲンダイ 2003.11.20 週刊読書日記 澤田ふじ子(作家)
神戸新聞 2003.11.12 気鋭の肖像 「歴史学者 勝田 至」
朝日新聞 2003.10.2 大阪版夕刊 テーブルトーク
読売新聞 2003.9.3 大阪版夕刊 読書面
産経新聞 2003.9.6 「歴史学者・勝田至氏に聞く」
新潟日報 中国新聞 他 2003.8.17 評者:斎藤英喜氏(仏教大学助教授)
死体が路傍・河原・野にあることが日常茶飯事だった中世。死者はなぜ放置されたか。「死骸都市」だった平安京で、ある時期にそれが急減することを探り出し、死体遺棄・風葬やそのゆくえなど、謎に包まれた中世の死者のあつかいを解き明かす。現代では当たり前とされる葬儀の習慣を根底から見つめ直す中世葬墓論。巻末に中世京都死体遺棄年表を付載。
〈主な目次〉Ⅰ=死骸都市・平安京(死体放置の状況/死体の分布)/Ⅱ=死体放置の背景(葬送と血縁/遺棄の場/京中の死人)/Ⅲ=貴族の葬送儀礼(1)(臨終から出棺まで/臨終と遺体の安置/入棺/出棺)/Ⅳ=貴族の葬送儀礼(2)(葬送/葬列/火葬/葬式の後)/Ⅴ=貴族の葬法(玉殿と土葬/葬法と霊魂/墓の選定)/Ⅵ=共同墓地の形成(諸人幽霊の墓所/二十五三昧/蓮台野の形成/鳥辺野と清水坂)/Ⅶ=死体のゆくえ(可能性の検討/輿の力?/変わりゆく葬儀)/中世京都死体遺棄年表
内容説明
死体が路傍・河原・野にあることが日常茶飯事だった中世。死者はなぜ放置されたか。「死骸都市」平安京で、ある時期にそれが急減することを探り出し、死体遺棄や風葬など謎に包まれた中世の死者のあつかいを解き明かす。
目次
死骸都市・平安京
死体放置の背景
貴族の葬送儀礼(臨終から出棺まで;葬送)
貴族の葬法
共同墓地の形成
死体のゆくえ
著者等紹介
勝田至[カツダイタル]
1957年、新潟県に生まれる。1988年、京都大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。現在、芦屋大学非常勤講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
鯖
六点
chang_ume
shi-ma
かっぱ