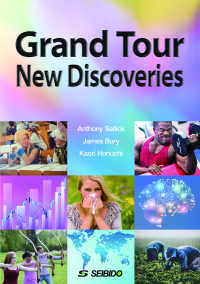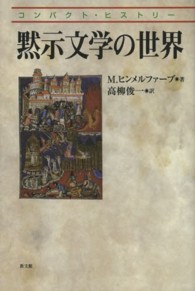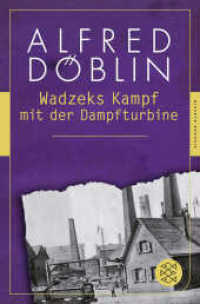内容説明
古代史の舞台=飛鳥。この地で仏教伝来から平城遷都まで、百数十年に亙って国家形成のドラマが演じられた。推古朝の文化と聖徳太子、蘇我氏と甘樫丘、大化改新、斉明天皇の土木と造園などを通して、飛鳥の魅力を語る。
目次
日本古代史にとって飛鳥時代とは何か
1 古代宮都の変遷(大化以前の都;天皇の世紀へ)
2 聖徳太子と蘇我氏(聖徳太子はなぜ「偉人」でなければならなかったか―蘇我馬子と聖徳太子;厩戸皇子の面影;厩戸王の政治的地位について―大山誠一著『〈聖徳太子〉の誕生』読後感;嶋の家と嶋の宮;中大兄と入鹿)
3 斉明天皇と石像物(斉明天皇の人物像;土木・造園と斉明女帝の素顔;瀧と噴水―飛鳥文化の国際性;有間皇子の問題の成立と斉明記;飛鳥の石造遺物と斉明天皇―酒船石遺跡と益田岩船)
4 天智天皇とその周辺(天智天皇;天智天皇と皇位継承法;中大兄の名称をめぐる諸問題;族長権の相続をめぐって―天智天皇と蘇我氏)
著者等紹介
直木孝次郎[ナオキコウジロウ]
1919年兵庫県に生まれる。1943年京都帝国大学文学部国史学科卒業。大阪市立大学教授、岡山大学教授、相愛大学教授、甲子園短期大学教授を経て、大阪市立大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。