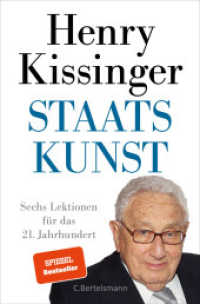内容説明
人は生まれてから、いかなる過程を経て大人になっていったのか。いのちの誕生から青年期を経て、老いを生きていくまでの一生の階梯を見つめ直す。また、日々の生活のなかで積み重なっていく経験の民俗的意味を問う。
目次
年を取るということ(年齢と人生の階段;近代家族の成立と子どもの教育;疾走する現代社会の行方)
1 いのちの誕生と成長(いのちの波と人生観;出産と育児の呪法;子ども観の変容と産育習俗;子どもの遊びの変容と自我形成の危機)
2 「青年」の民俗(「青年期」の誕生―若者組の登場;村の「青年期」―若者組の諸活動;「青年」の歴史民俗誌;「青年」と民俗学)
3 大人と老人の民俗(大人と仕事―経済的労働:休憩と創造;大人のつとめ―社会的奉仕:伝達と継承;老いの境涯―老いの力と自由;老いと死―生と死の媒介者)
著者等紹介
飯島吉晴[イイジマヨシハル]
1951年、千葉県に生まれる。1982年、筑波大学大学院歴史・人類学研究科博士課程単位取得退学。現在、天理大学文学部教授
宮前耕史[ミヤマエヤスフミ]
1969年、群馬県に生まれる。2003年、筑波大学大学院歴史・人類学研究科博士課程単位取得退学。現在、啓明大学校国際学大学日本学科招聘専任講師(韓国)
関沢まゆみ[セキザワマユミ]
1964年、栃木県に生まれる。1988年、筑波大学大学院地域研究研究科修士課程修了。現在、国立歴史民俗博物館准教授・総合研究大学院大学准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
2
民俗学という学問の現代的意義は、効率重視のCVS型社会で、待つことができない世の中になっている過剰サービス社会の下で、人間発達においては待てなければ教育などできないことを教えてくれる(43ページ)。通過儀礼は発達段階のステップアップを期待している儀式であるが、現代は契約できにくい相手を信頼できにくい世の中である。自治とは、自己犠牲と奉仕の精神(180ページ)。現代は地方自治というが、果たしてこうした精神があるだろうか。エゴイズムではないか。民俗学でも地域固有の文化や生物多様性へのまなざしが重視されている。2012/12/04