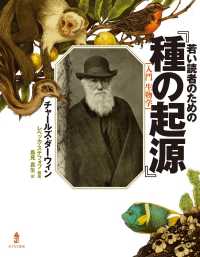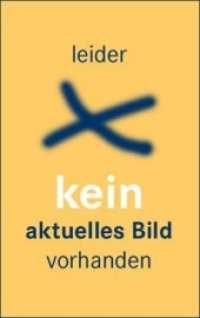出版社内容情報
長く平和が保たれた時代に、列島はどのように変化したのか。将軍と側近による幕政の主導、通貨・物価問題、藩政改革、貿易体制・対外認識の変貌などに着目し、五代綱吉から田沼意次の時代までの政治と社会に迫る。
内容説明
長く平和が保たれた時代に、列島はどのように変化したのか。将軍と側近による幕政の主導、通貨・物価問題、藩政改革、貿易体制・対外認識の変貌などに着目し、5代綱吉から田沼意次の時代までの政治と社会に迫る。
目次
第1章 将軍専制と社会
第2章 将軍吉宗の改革政治
第3章 長崎貿易と国内市場をつなぐ商人集団
第4章 日朝関係と対馬藩
第5章 貨幣改鋳と経済政策の展開
第6章 「改革」文化の形成
第7章 学問の場でつくられた対外認識
著者等紹介
村和明[ムラカズアキ]
1979年、愛知県に生まれる。現在、東京大学大学院人文社会系研究科准教授
吉村雅美[ヨシムラマサミ]
1982年、埼玉県に生まれる。現在、日本女子大学文学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
13
綱吉から田沼時代までを扱う論集。終章で「変わらないために変わる時代」とまとめているが、享保の改革という特大のものを含め、貨幣制度や諸藩の藩政改革など幕藩体制の枠組みを守るための改革が繰り返された時期であり、こうした変化を受け止めるだけのレジリエンスがあったことが、幕府の安定期を生んだのであろう。また綱吉、家宣、吉宗と養子将軍が相次いだ時代でもあり、甲府系、館林系、紀州系と将軍の代替わりごとにその側近層も入れ替わることで、人事の活性化が起こっていたことも、変化への対応力を高めたのではないだろうか。2024/12/06
アメヲトコ
7
2024年元日刊。シリーズ第2巻は綱吉期から田沼時代まで、対外危機の薄い安定期が取り上げられます。「変わらないために変わる時代」(酒井)とはまさに言い得て妙。将軍側近と商人・大名をつないだ碁打ちの役割(村論文)とか、「改革」という用語の同時代的な意味合い(小関論文)とか、色々と勉強になりました。2024/06/13
Go Extreme
1
泰平のなかの変化と対応 将軍専制と社会:綱吉側近 家宣側近 吉宗側近 碁打ちの関与 将軍吉宗の改革政治:改革政治の概要 大坂からみた吉宗政権 享保16年の転換 長崎貿易と国内市場をつなぐ商人集団:近世初期の貿易商人 貿易仕法の模索と商人の動向 長崎会所を軸とした運営体制の形成 会所貿易に関わる商人と商業機関 日朝関係と対馬藩 貨幣改鋳と経済政策の展開 「改革」文化の形成 学問の場でつくられた対外認識 18世紀末の日本を凝縮する夷酋列像 変わらないために変わる時代:産物・国益 対外危機と捕鯨 体制危機の前夜2024/02/22