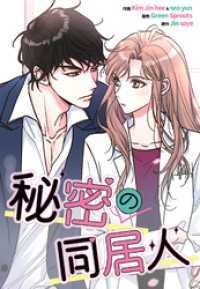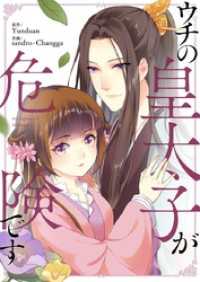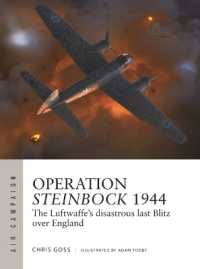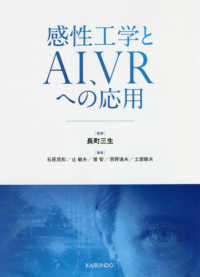出版社内容情報
南北朝・室町時代、鎌倉府の首長「鎌倉公方」足利氏と、それを支えた「関東管領」上杉氏。君臣の間柄だった両者は、東国の動向や京都とのかかわりが絡み?対決?の結末をたどる。自立へ向かう100年の東国史を解きほぐす。
内容説明
南北朝・室町時代、鎌倉府の首長「鎌倉公方」足利氏と、それを支えた「関東管領」上杉氏。君臣の間柄だった両者は、東国の動向や京都とのかかわりが絡み“対決”の結末をたどる。自立へ向かう一〇〇年の東国史を解きほぐす。
目次
プロローグ 足利氏と上杉氏
1 鎌倉公方、東国に立つ(内乱のなかで;関東執事畠山国清の消長 ほか)
2 紛擾と争乱の東国(闘う東国寺社;氏満と義満 ほか)
3 応永の乱から上杉禅秀の乱へ(列島支配の再編;応永の乱 ほか)
4 鎌倉公方足利持氏と関東管領上杉憲実(上杉禅秀の影;足利持氏の専制 ほか)
エピローグ 足利持氏と上杉憲実のこどもたち
著者等紹介
植田真平[ウエダシンペイ]
1985年、東京都に生まれる。2012年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士(文学)。現在、宮内庁書陵部研究職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
114
享徳の乱を知らんと欲さば永享の乱を知らねばならぬ、永享の乱を知れば次は上杉禅秀の乱を知らんずばおられぬ。鎌倉公方と関東管領の対立と言うよりは、京都の室町幕府と鎌倉公方の対立にしか思えぬのは、先に読み終えた方々の仰るとおりである。寧ろ関東管領はこの段階だと、鎌倉と京の間に挟まれた現地代理人ぽくて、気の毒に思えてくる。関東公方とて、本人たちの野望もあるが、関東に出仕する武士達の神輿にならざるを得ないのである。しかして、次巻ではついに「享徳の乱」に取り掛かるのであった。今度は関東管領が分裂…はぁ…。2023/02/10
MUNEKAZ
19
鎌倉公方と関東管領の対決というよりは、鎌倉府と室町幕府の対立といった内容。烏帽子親子の足利氏による東西の分掌という非常に危うい支配体制と、その仲介役として権力を振るう関東管領の存在を簡潔に描く。この微妙なバランスが崩壊するきっかけは上杉禅秀の乱。関東管領と公方の力関係が逆転し、さらに幕府が関東に介入する端緒となる。一度壊れた関係は元に戻らず、永享の乱で破綻を迎える。また東西対立の要因を、幕府側の猜疑心による過剰反応に求め、しばしば言われる鎌倉公方の「野心」「好戦性」という見方を戒めているのも印象に残った。2022/04/25
翠埜もぐら
16
南北朝騒乱、観応の擾乱そして直義派の南朝接近と、成立期から不安定だった室町幕府が東国の要として置いた鎌倉府。幕府の出先機関としてでなく、独立した行政府であることを強く意識していく、いや南朝衰退後、東国の武士たちと渡り合っていくために、そうならざる得なかったため京都と乖離していくわけです。しかし持氏と義則と言う強硬派が双方でトップに立っちゃったのが運の尽きだったのでは?上杉憲実は基本幕府に従いつつも両者を取り持つべく努力するということになっていますが、戦国期の将として優柔不断の気弱男のように思えるのですが2022/07/25
組織液
15
小国浩寿先生の『動乱の東国史5 鎌倉府と室町幕府』よりも近年の研究成果が反映された室町東国史の一般書です。鎌倉公方の‘’野心‘’については再考が必要というのは本当にその通りだと思いました。上杉禅秀の乱に一番興味が湧きましたね。2023/11/17
Toska
12
「対決」だけでシリーズができてしまうのだから東国史も物騒だ。とは言え、室町幕府vs鎌倉府・鎌倉公方vs関東管領の対立軸で単純化することなく、丹念な状況整理を試みている点に好感を覚える。関東管領は寧ろ鎌倉公方と協調していた時期の方が長く(本来はそれが当たり前でもある)、深刻な対立に陥ったのは最終段階のみ。ただ、自分が仕えるのは京都なのか鎌倉なのか?を問われる局面が生じた時、後者に踏み切れなかったのがこのシステムの限界か。2023/03/23