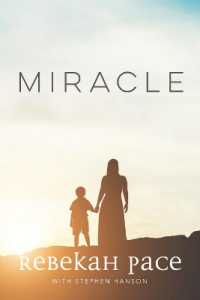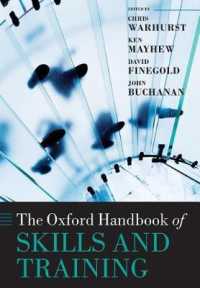出版社内容情報
「応仁の乱に就て」一〇一年目の地平から―プロローグ/室町時代の国のかたちと幕府の支配―一〇〇〇万人の列島社会と首都京都(中世後期の国のかたち/室町の国のかたちができるまで―室町幕府財政の形成過程/変容する国のかたち―室町幕府財政の再建から/国のかたちが失われたあとで)/御家人制の消滅(御家人制のゆくえ―室町幕府成立までの前提/御家人制壊滅と国家的軍務の変質/臨時役財源の途絶と代替)/「守護在京制度」とは何か(守護を兼ねる在京大名/大名の在京形態と幕政参与/大名在京の展開と矛盾)/京の武家政権と禅宗寺院(京都の禅宗/二つの菩提寺と足利直義/天龍寺の創建)/首都の統治と五山禅宗(京都五山の成立/五山仏事の機能①―戦乱と鎮魂/五山仏事の機能②―飢饉と鎮魂)/コラム1 〈変貌〉する相国寺と義満/都市の支配と宗教儀礼(攘災と祝祭/王朝の伝統、室町殿の伝統)/室町幕府と皇位・皇統(鎌倉後期以来の皇統問題/足利尊氏・義詮期における皇統・皇位/足利義満期における皇位・皇統/足利義持期における皇位・皇統/足利義教期における皇位・皇統/足利義政期以降の皇位・皇統)/室町社会と酒―『看聞日記』を中心に(室町幕府のイメージ/伏見宮家と酒/室町期京都の人々と酒/遊蕩を支えるもの)/コラム2 伏見宮家の一年と酒/コラム3 麹づくりと「酒屋交名」/コラム4 室町将軍の血と酒/コラム5 宮廷と宮家の酒宴・酒乱/北山・室町文化論(文化史研究の現状と課題/足利義満期の文化―職人の再生/足利義持・義教期の文化①―婆娑羅からの卒業/足利義持・義教期の文化②―女房衆が経済をまわす/伝統的な文化への回帰)/室町時代、その後―エピローグ
内容説明
人口一千万人の列島社会で、室町殿を中心に公家・武家・寺社が結集し繁栄する首都京都。人やモノの往来の活性化で社会も大きく変化した。天皇家や御家人制の行方、寺社勢力の変質、幕府の資金源に迫る新しい室町時代史。
目次
1 室町時代の国のかたちと幕府の支配―一〇〇〇万人の列島社会と首都京都
2 御家人制の消滅
3 「守護在京制度」とは何か
4 京の武家政権と禅宗寺院
5 首都の統治と五山禅宗
6 都市の支配と宗教儀礼
7 室町幕府と皇位・皇統
8 室町社会と酒―『看聞日記』を中心に
9 北山・室町文化論
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
MUNEKAZ
アメヲトコ
田中峰和
吃逆堂
-
- 洋書
- Miracle