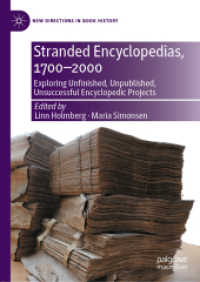出版社内容情報
15世紀後半、2つの争乱を契機に室町幕府は崩壊の道へ―。京都での東西両軍の対立に至る政治過程や、大乱の様子と乱後の情勢を西国にも目を向けて叙述。将軍家を二分した政変を経て、乱世へと向かう時代を通観する。
内容説明
十五世紀後半、二つの争乱を契機に室町幕府は崩壊の道へ―。京都での東西両軍の対立に至る政治過程や、大乱の様子と乱後の情勢を西国にも目を向けて叙述。将軍家を二分した政変を経て、乱世へと向かう時代を通観する。
目次
室町幕府の運命を決した争乱―プロローグ
1 斜陽のはじまり(嘉吉の変;足利義政の登場 ほか)
2 中央における応仁・文明の乱(義政と足利義視;畠山義就の帰還 ほか)
3 地方における応仁・文明の乱(北陸地方;東海地方 ほか)
4 戦後の世界(武家社会の再建;公家社会の衰退 ほか)
5 国一揆と明応の政変(各地で頻発する一揆;継続される応仁・文明の乱の対立構図)
再び争乱の世へ―エピローグ
著者等紹介
大藪海[オオヤブウミ]
1982年、千葉県に生まれる。2009年、慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学。現在、お茶の水女子大学基幹研究院人文科学系准教授、博士(史学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
14
応仁の乱から明応の政変までの概説書。複雑極まりないこの時期の政治史を、丁寧に説明してくれているが、それでも頭は混乱気味(ただ足利義政がアカンのは十分伝わってきます)。幕府の中の政争では同盟していても、大名家としては敵対するというのが頻発し、お互いに妥協点が見いだせなくなっていくカオスが描かれている。また地方における乱の波及にも章を割いており、短いながら西国の情勢を1国ずつ説明しているのも興味深い。細川一門の治める四国や大内氏の領国が比較的安定しており、戦国前期の主役たちがこれらから躍り出たのも納得である。2021/03/11
吃逆堂
5
応仁の乱の特質を地方の争乱との連鎖に見出し、国ごとの展開も丁寧に叙述する。叙述も衒いがなく落ち着いていて人物評も豊かであり、多少の煩雑さはしかたないとしても総じて安心して読める。2022/01/28
フランソワーズ
4
応仁・文明の乱の通史。著者が語るように、京と畿内周辺ばかりに目が向けられることが多い一般書が多い中、それ以外の地域にも言及しているのが良かった(各地方の史料残存の差が内容に反映されているけど)。タイトルにはなっている明応の政変の方は、分量がかなり薄かったのが残念。2024/12/07
黒蜜
2
興味深い。『応仁の乱』から始まった感じの中世ブーム。大河ドラマやマンガのネタにも中世が取り上げられるが、最近の研究は進んできてるので、新たな発見にびっくりすることしきり。2025/09/06
Toska
2
『応仁…」と言いつつ、実は嘉吉の変から語り起こされていて、義教時代に遡る対立の起源がよく分かる(逆に明応の政変は駆け足で終わってしまった印象)。中央情勢のみならず、地方における乱の展開を概観するというのは興味深い取り組みと思う。各地で東西両勢力が入り乱れて戦う有様は関ヶ原を想起させるものがあるが、関ヶ原もあの決戦がなければ応仁・文明のようにダラダラと争乱状態を続ける可能性があったのか、逆にそうならなかったのはどうしてか…等々と考えるのも楽しい。2021/07/15