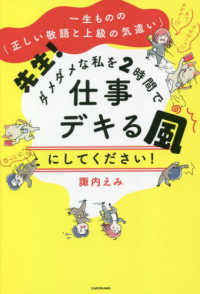内容説明
倭国はどのように成立したのか。旧石器時代より飛鳥・藤原京にいたる列島の歴史と文化を、考古学・文献史学・人類学の最新成果で読み解く。東アジアとの公流を通じ、個性豊かな文化が育まれた日本のはじまりを描く。
目次
日本列島の文化のあけぼの―プロローグ
1 旧石器時代の日本列島
2 縄文人の生活と社会―高度な狩猟・採集文化
3 農耕社会の形成―弥生文化の成立と展開
4 倭国と前方後円墳の登場
5 倭の五王の時代
6 雄略朝から継体・欽明朝へ
7 飛鳥・藤原京の時代―律令国家の胎動と成立の時代
日本列島の北と南の文化―エピローグ
著者等紹介
木下正史[キノシタマサシ]
1941年東京都に生まれる。1964年東京教育大学卒業。現在、東京学芸大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はちめ
12
著者は経歴からすると飛鳥時代あたりの専門家のようだが、飛鳥時代に関する記述は第2巻への触り程度で、大和朝廷成立以前までが主な内容になっている。あえて専門家以外を担当させて分かりやすいものとしようとした意図は理解できる。ただ、弥生後期から古墳時代にかけては、文字を含まない発掘資料が増えて分かりにくい。おそらくこれは、著者の責任ということではなく、日本古代史自体が抱えている課題だと思う。☆☆☆☆2020/05/05
スプリント
9
一から日本の歴史を学びなおそうと思い本シリーズを手にとりました。 時代により古墳の形状が代わり、人口の増加、生活圏の拡大とともに古墳のサイズが小さくなっていく。 大陸とのつながりを知ると同時代の中国がいかに先進国だったかがよくわかる。2024/01/13
たけはる
6
資料用。びっくりするほど忘れてて、もっかい日本史の授業受け直したい、と思いました……。2018/11/07
讃壽鐵朗
4
典型的な古代史総説2021/11/02
はちめ
3
縄文後期から弥生への移行期については、稲作開始時期の問題などかなり常識が変わりつつあることが分かります。ただ、一世紀から三世紀にかけて、邪馬台国の成立から大和における王権の成立にかけて、日本列島で何が行ったかについては推測さえ十分にできていない。画期的な発掘を待つしかないみたい。2013/08/03
-

- 電子書籍
- STYLE WAGON 2023年7月号