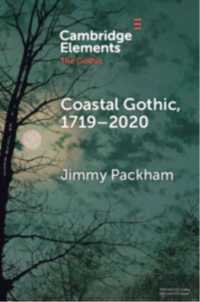内容説明
室町幕府の東国統治体制は、鎌倉公方の分裂で弱体化し、やがて伊勢宗瑞(北条早雲)の登場にいたる。享徳の乱以降、関東全域を巻き込んだ争乱の時代を、連歌師ら文化人の関東下向や東国村落にも触れつつ新視点で描く。
目次
1 享徳の大乱
2 堀越公方の成立
3 景春の乱と都鄙和睦
4 両上杉の抗争
5 連歌師・詩僧たちの関東下向
6 十五~十六世紀初めの東国村落
7 永正の乱
著者等紹介
則竹雄一[ノリタケユウイチ]
1959年、東京都に生まれる。1994年、一橋大学大学院博士後期課程単位取得退学。現在、獨協中学高等学校教諭、明星大学非常勤講師、博士(社会学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
13
戦国時代の先駆けである関東の動乱を追う。ここ迄戦国時代は応仁の乱よりむしろ享徳の乱から始まるとの説を読む事が多かったが、本書著者はこれを採らない。むしろ中世から近世への劃期としての文化論村落論を以てこれに答える。伊勢宗瑞(嘗て彼は北条早雲を自称したことがない)の下剋上論は講談話である事は既に定説である。太田道灌の京から下った文化人との交流、豊島氏との戦も東京の地名が頻出し面白い。秩父緑泥片岩を用いた板碑の考証は、散歩が楽しくなるが、「動乱」の記述は、上杉諸流とその家宰を巡る争いであり、頭には入り難かった。2021/12/11
coolflat
11
太田道灌の謀殺は、両上杉氏の抗争を生み出すことになった。これが長享の乱である。では道灌暗殺にいたる原因は何であろうか。一つには、山内上杉氏(顕定)と扇谷上杉氏(定正)の対立があった。二つ目には、扇谷上杉氏家臣団の内部対立の存在があったと見られる。道灌を直接殺害したのは曽我兵庫助であり、扇谷上杉定正の養子朝良の執事を務め、道灌暗殺後に河越城代となり、その子豊後守祐重は江戸城代になったという。道灌に替わって扇谷上杉家の家政を取り仕切る立場になったとみられることから、扇谷譜代層の主導権争いがあったと考えられる。2024/01/20
陽香
2
201301102017/06/11
吃逆堂
1
史料が乏しく東国史の穴と言われるこの時代だが、そういうことを感じさせない叙述。考古の成果も存分に盛り込むあたりも、著者ならではか。前半、文章がかため。2013/04/06