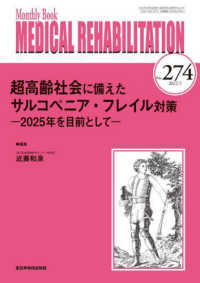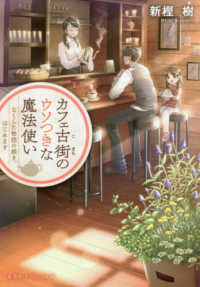内容説明
東国国家樹立を目指した平将門の乱は何をもたらしたのか。将門追討で功をなした人々の系譜を辿り、保元・平治の乱にいたる東国武士団の動勢に迫る。坂東の水上交通や自然環境にも注目し、中世成立期の東国を描く。
目次
1 坂東の歴史風景―古代から中世へ
2 平将門の乱
3 新皇将門の敗北
4 勝者たちの歴史―将門以後
5 奥羽の地域社会と前九年・後三年合戦
6 東国武士団と保元・平治の乱
著者等紹介
鈴木哲雄[スズキテツオ]
1956年、千葉県に生まれる。1981年、東京学芸大学大学院修士課程修了。現在、北海道教育大学教育学部教授、博士(史学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
14
20頁。蝦夷経営における陸奥国と坂東の八カ国との役割を区分けした「坂東八カ国」体制は、795年以降、藤原朝獦(藤原仲麻呂の子)によって整備された。それによって、蝦夷経営の最前線基地として上野・下野の両国(東山道に属す)は、東海道に属した常陸国などとともに「坂東」とされた。その坂東から多賀城への、蝦夷征服のための人員や物資が輸送されるルートには下野国からの山道と、常陸国からの海道があった。平将門の乱や平忠常の乱など十世紀以降の東国の動乱は、九世紀までの古代坂東の政治的・地理的な位置を前提に展開していく。2022/11/22
りー
11
正直、情報量が半端無くて頭パンパンですが、おぼろ気な輪郭は見えました。東国前史→平将門乱→平忠常乱→前九年・後三年→保元・平治まで。図、写真、地図、系図も豊富でイメージしやすい。とりあえず、馬が大事じゃないか!ということが分かりました。東国を支配地域に組み込むにあたってはまず、牧が置かれる。それをつかさどるのが馬寮(本来は諸国馬牧や諸国繋飼馬、勅旨牧から貢上された官馬の配分や飼養などをつかさどる役所)。そして、水運。各水系の支配権争いとして戦いがおこる。色々通説と違う視点をもらえて面白かったです。2020/04/20
青雲空
9
武士とは東国じばえでなく京都の京武者が下向し地元豪族に入り婿して発生していったということ一つとっても、昔の教科書とは違っている。 中高年にとって日本史のアップデートは必要だ。 そして10世紀の地震、火山噴火、天変地異の多さに驚く。そら乱も起こるわ。 千年ぶりに日本列島が天変地異期に入ったようで、これからが案じられる。 2024/02/25
こじこじ
2
途中かなり期間空いたが読了 平将門の乱そのものというより平安時代中期から後期にかけての東国武士団の動向について記述 奥州について北緯39度、40度でラインを引いた3地域に分ける見方は初めての学びとなった また東北の蝦夷の風俗が鶴の恩返し成立に関わるというコラムも興味深かった 東国の通史らしく地域のつながりや時代のつながりを強く意識しながら読むことができた この本に限らないが系図類を巻末にまとめてもらえると我々素人にもより分かりやすくなるのにと思う2023/07/19
keint
2
タイトルの通り天慶の乱(平将門の乱)から平忠常の乱、前九年・後三年の役、荘園公領制の確立、保元・平治の乱までを東国の視点から概説している。 今昔物語集の25巻で描かれている時代(天慶の乱~前九年の役)と基本的には重複しているので、この巻を読むための歴史の予備知識はこの本でつけられる。 ただ、保元・平治の乱は駆け足気味で説明されていたため、これは別の書籍を参考にしたほうがよい。2019/06/04
-
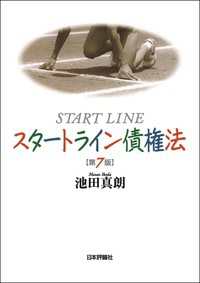
- 電子書籍
- スタートライン債権法