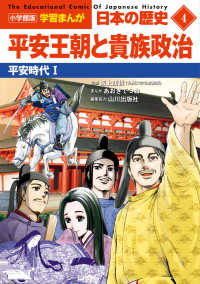内容説明
国家支配の基本となる暦。六世紀に中国から伝来するが、天体運動との差が生じやすく、太陰暦は改暦を必要とした。やがて日本独自の暦が作られるなど、“暦”に携わった天文研究者たちの活躍を辿り、歴史の真実に迫る。
目次
1 暦法始行とその周辺(自然暦;暦の発生の条件 ほか)
2 唐暦行用の時代(儀鳳暦;一番古い暦 ほか)
3 日本人による暦法(南蛮人の渡来;グレゴリオ暦 ほか)
4 西洋天文学の受容(麻田剛立;長崎の天文学 ほか)
5 明治の改暦とその後(明治初期の編暦と頒暦;太陽暦の施行 ほか)
著者等紹介
内田正男[ウチダマサオ]
1911年小田原に生まれる。1943年専検合格。1944年東京天文台に入る。1982年退官(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
中将(予備役)
1
土御門家に関する展示を見る前の勉強に読む。暦の歴史に生活の継続性と政治性を感じた。宣明暦とともに世襲で長く天文や暦の道を守ってきた土御門家、一時は土御門神道を学び日食とずれて生活上も不便と授時暦を推しその限界を知って後貞享暦を作った渋川春海、未熟で続けなかった渋川家、非実証的に暦を京と古来の法に取り戻した土御門家と宝暦暦、流布する私的な暦、西洋にも学んだ寛政改暦、なぜか不定時法が入る天保暦、明治の太陽暦、残る時候と失敗した世界暦。2023/04/16
霹靂火 雷公
1
明快な筆致と一貫して「科学的」な見地の為か、難無く読めた。順を追って各暦法の特徴を踏まえた上で、歴史的な経緯を人物を中心に描いているので、文学的にもスリリングな感覚が味わえた。映画『天地明察』では「何故だ!」で終わっていた三暦勝負で宣明暦のみ的中した理由などが明確に示されていてよかった。筆者の旧暦に対する嫌悪が占術者として引っ掛かっていたが、解説でそれがフォローされていたので後味も悪くなかった。参考文献だけでなく、初学者向けの資料も挙げられているのは嬉しい。2012/12/24
wang
0
日本で古来より使われて来た暦を順を追って説明。特に古い暦は正確性に乏しいため何度も改暦されたが、その改暦がなぜ必要だったのか改められた暦がどのような特徴を持っているのか科学的根拠に則り詳述している。特に、改暦に関わった人物に焦点を当て記述しているのが素晴らしい。多くの優秀なる日本人が努力の末に作り上げた暦に敬服する。2013/03/06
dahatake
0
日本での天文と暦の歴史の話。 今の暦がキリスト教の由来といっても、実害は殆ど無いし。陰陽もある種の宗教的なものだし。確かに平安の昔は暦の位置付けは、全然異なるし、平安京ではそうだったのであろう。 能力なき人が意思決定にあたることになった際に、実際に日食が外れるなどしたのに、その言い訳が幼稚で現代と変わらない人が見える。逆に言えば、そうした人でも機能するように組織としては対応すべきなんだと思う。2024/06/21