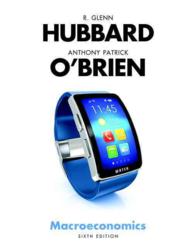内容説明
百年前に極東で勃発した日露戦争。その様子は通信網により翌日には欧米諸国で報道された。この戦争を国際政治の力学と情報・報道戦の側面から見直し、各地での作戦や軍事システムを豊富な図表を駆使して描き出す。
目次
戦争と情報―プロローグ
1 日露戦争への道
2 ロシア地上軍撃破と制海権確保のための戦い
3 陸海での決戦と戦争の終結
4 日露戦争の世界史的意味
5 日露戦争と日本軍
戦争による歴史観の変容―エピローグ
著者等紹介
山田朗[ヤマダアキラ]
1956年大阪府に生まれる。1985年東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。博士(史学)。現在、明治大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
40
第4部の「日露戦争の世界史的意味」が読み応えがある。この戦争は世界的な英露の対立からうまれたもので、海底ケーブル網を構築した英国と同盟したことで情報通信戦で日本は優位に立った。戦費は外債で調達したが、ここでも日英同盟がプラスに働いた。日本をアジアの希望の星とする論調を作ったのは英国系通信・新聞社。戦後、乃木希典や東郷平八郎は神格化され、白兵主義と戦術至上主義を批判できなくなった。ひいては織田信長や豊臣秀吉の奇襲奇策のイメージ創作にもつながったという。勝利は逆に真実を見えにくくすると言うことの典型ですな。2018/03/16
MUNEKAZ
16
日露戦争を日本とロシアの間だけではなく、英米仏独の列強各国の動きから見た一冊。極東で起きた戦争が、海底ケーブルや電信網の発達により世界各国にリアルタイムで送信されたことの重要性を指摘。日英同盟を結び、英米メディアの好意を得たことが、外債調達などで日本の有利に働いた。また戦争によるロシアの弱体化は、英露(+仏)間の対立緩和に繋がり、英仏露と独墺の対立という第一次世界大戦の図式となる。日露戦争が、20世紀の歴史に与えたインパクトを簡潔にまとめており面白い。色々な意味で日露戦争の結果があっての両世界大戦ですな。2021/11/26
Toska
6
高校時代、世界史の先生が「日露戦争はイギリスの代わりにロシアと戦わされたようなもの」と言っていたのを思い出す(今考えると、すごい授業だったと思う)。この時期、ボーア戦争の泥沼にはまり込んでいた大英帝国にとって、宿敵ロシアを極東で引き受けてくれる日本はこの上なくありがたいパートナーだった。日英同盟なくして日露戦争は戦えなかったことがよく分かる。一方で、「日本はイギリスに操られていた!」的なセンセーショナリズムにも陥らず、当事者たる日本とロシアの主体性がしっかりと分析されている。良書。2022/05/19
風見草
5
軍事史に強い著者であるため具体的な兵器や戦術や戦訓についても言及されています。しかし、本書の最大の特徴は、戦争の展開や同盟・外交関係だけでなく、当時の世界的な電信網の発展による各国の新聞報道を意識的に取り上げていることです。世界レベルのメディアや各国紙の論調による世論誘導などのマス・メディアによる戦争でもあった(その点でも近代的であった)という視点がユニークでおもしろかったです。2009/09/10
kiri_same
4
日露戦争が勝ち戦だったことで、誤った戦訓を得てしまったという話。日本海海戦は最強のバルチック艦隊を打ち破ったと認識していたのだけれど、実のところはロシア本国から遠路はるばるやってきた旧型混じりの艦隊をボコボコにしたというのに驚いた。日露戦争での情報通信の役割が大きかったのにもかかわらず全く軽視されてしまったり、勝った戦術に固執するシステムが形成されてしまったりと、これでは果たして勝ったことが良かったのだろうかとすら思ってしまう。2018/06/24
-
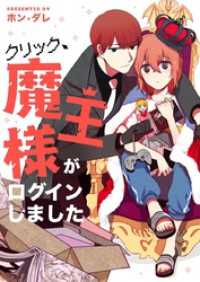
- 電子書籍
- クリック、魔王様がログインしました【タ…
-

- 電子書籍
- 穢れを祓って、もふもふと幸せ生活2【電…