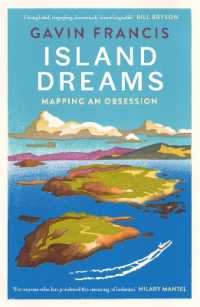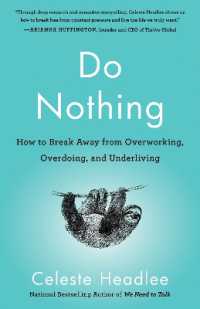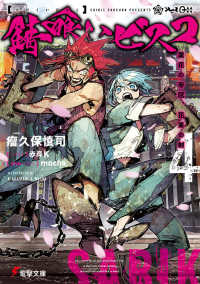出版社内容情報
天下人豊臣秀吉に抗った戦国大名北条氏の本城小田原城。敗れはしたが、今日に至るまで堅固な要害として名高い。しかし、実際には何度も落城を経験し、秀吉の軍門にも降っている。そのような小田原城が何故「難攻不落」と称されるのか。発掘調査成果と文献史料・絵画史料などを分析し、北条氏の志向性から難攻不落と呼ばれた真相を明らかにする。
内容説明
天下人豊臣秀吉に抗った戦国大名北条氏の本城小田原城。発掘調査成果と文献史料・絵画史料を駆使し、小田原の城と城下の景観にアプローチ。敗れながらも小田原城が「難攻不落」と称されるのは何故か、その真相に迫る。
目次
なぜ小田原城は「難攻不落」と言われるのか?―プロローグ
北条氏以前の小田原古城―都市「小田原」への寄生
白亜の天守聳える小田原城―小田原新城の誕生
二代氏綱による小田原整備
記された戦国期の小田原
発掘調査でよみがえる戦国期小田原城
戦国大名としての北条氏
戦国都市小田原の景観をよむ―エピローグ
著者等紹介
佐々木健策[ササキケンサク]
1974年、埼玉県に生まれる。現在、小田原市文化部文化財課副課長、慶應義塾大学・國學院大學非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
116
小田原城について当然視されてきた常識を、次々と破壊していく。「難攻不落の城」との表現は明治に成立したもので、実際は秀吉による攻撃を含め7回攻められ4回落城しているという。有名な「総構」は大構が正しく、現在の城郭は江戸初期の大地震被害から立ち直った姿であり、戦国時代の実像は上書きされてしまった。しかし後北条氏が5代にわたりインフラと城の整備を重ね、関東の首都として栄えた有様が、敗北を知らぬ大都市とのイメージを生んだと見る。畿内を根拠地とする秀吉が、そんな独自の発展を遂げた小田原を許せなかったことこそ当然か。2024/07/22
ポチ
45
以前総構えの一部を歩いた事があるが、あの迫力には驚きました。また北条氏時代の遺構を巡ってみたいです。2024/07/02
鯖
18
関東管領職等を通じ関東の身分秩序に組み込み、「他国之凶徒」からの脱却を図った氏綱。大森氏の既得権益の場である大窪から離れ、東側の未発達地域に正方形の地割で都市形成を行ったという指摘はほーんってなった。阿仏尼の十六夜日記の記述によれば現在の小田原には海女の家が数件ある程度とのことで、ほーんてなった。手延べのかわらけからろくろ左回転かわらけへの移り変わりとか金箔が押されるかわらけはその二つに限定されてるとか、知らないことばっかりでとても面白かった。また読む。2024/07/14
サケ太
16
小田原城、『難攻不落』のその理由。小田原城の成り立ちから、歴代城主。そして後北条氏へと至った経緯。個人的に北条氏綱が異常に好きだったため、彼がなぜ北条氏を名乗ったのか、という理由も書かれており面白い。なぜ北条氏は豊臣家によって滅ぼされたのか。北条氏の目指したものの、豊臣家の目指したものの不一致。城には、土地には歴史がある。改めて小田原城を訪ねたいと思った。2024/08/31
アメヲトコ
12
2024年元日刊。北条氏の本拠として名高い小田原ですが、今残っているのは寛永小田原地震以降の姿であって、必ずしもイコールではありません。本書は絵図や文献、発掘成果などを駆使して、現状からレイヤーを一枚ずつめくるようにして戦国期の小田原の姿を復元しようとする一冊です。室町期の手法に則って都市形成を行った氏綱期に対して独自の路線を進み始めた氏政期という評価は興味深いところです。前者について、正方位の街路をもって「京都らしい」とする点は本当かなとも思いますが。2024/06/05