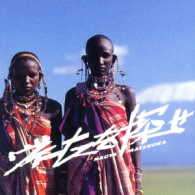出版社内容情報
今から約4500年前に西アジアで発明され、美しい珠や器となって、はるか東方へともたらされたガラス。それらはどのような人物が入手し、そこにはいかなる意味があるのか。シルクロードの東西交渉や、ユーラシア諸社会の栄枯盛衰、日本列島と大陸の交流などを、出土したガラス製品から読み解き、活き活きとした古代の人々の姿を映し出す。
内容説明
はるかな旅路を越え古代社会を映し出すガラスの魅力!
目次
美しい古代ガラスの世界―プロローグ
ガラスの特性と歴史
蜻蛉珠と草原シルクロード
漢代のガラスとユーラシアネットワーク
弥生社会のガラスと大陸との交流
激動のユーラシアとガラス
ガラスが見てきたユーラシア―エピローグ
著者等紹介
小寺智津子[コテラチズコ]
愛知県に生まれる。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。現在、国士舘大学・駒澤大学・創価大学非常勤講師、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- S級勇者の友人A ドラゴンノベルス
-
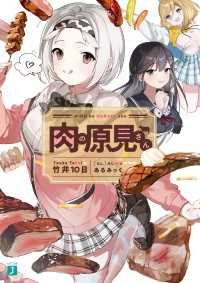
- 電子書籍
- 肉の原見さん MF文庫J