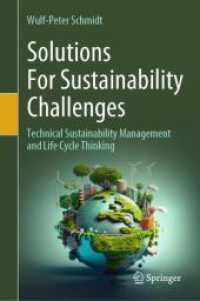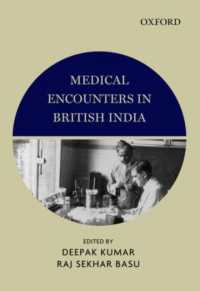出版社内容情報
香りを聞く芸道「香道(こうどう)」は中世日本で花開いた。香木の香りを鑑賞し、違いを聞き分けて楽しむ遊びの源流を探り、「香道の祖」とされる三条西実隆をはじめ香文化に関わった人々の姿を、彼らの日記などから浮き彫りにする。また、舶来品の香木や天皇が作る薫物(たきもの)が贈答用として珍重され、朝廷や武家のなかで政治的な役割を担った側面も鮮やかに描き出す。
内容説明
香道は中世日本で花開いた。香木の香りを鑑賞し、違いを聞き分けて楽しむ芸道の源流を探り、香文化の発展に深く関わった人々の姿を浮き彫りにする。また、香木は贈答品として使用され、政治的役割を担った側面も描く。
目次
香道とは―プロローグ
香道前史―古代から南北朝時代
香道の黎明―禁中の香会と組香
二人の始祖―三条西実隆と志野宗信
香木の献上
天皇からの薫物・匂い袋下賜
香道の発展―江戸時代の香会と組香
香道の黎明とその後―エピローグ
著者等紹介
本間洋子[ホンマヨウコ]
群馬県に生まれる。武蔵大学大学院人文科学研究科博士後期課程単位取得退学。現在、武蔵大学総合研究所研究員、博士(人文学)、臭気判定士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アメヲトコ
8
茶道や華道に比べるといくらかマイナーな香道の世界について叙述した一冊。競技的な側面のある聞き香の成立過程や、天皇からの下賜など政治的贈答品としての香の役割などについて、貴族の日記などを素材に論じられます。香と文学を結びつけることになる源氏香というのはなかなかの発明ですね。それからかの有名な蘭奢待、あれは「東」「大」「寺」の3文字が隠されたネーミングだったことを今更知りました。これだけ和の伝統を感じさせる世界でありつつ、香木そのものは国産できず全て輸入品で、異国の香りであるというところも面白い。2021/05/15
六点
8
恐らく、仏教が日本に入って以来、「香を炊く」行為は連綿と続いていたのだが、「香道」として成立したのは室町時代中期から後期にかけて、と、言うのが定説であったのだが、それ以前にも「香を聞く」遊びは皇族周辺から広まっていた。では何故、香道の祖と言うものができてしまったのか?は本書で謎が解かれている。「香道」や「香」が皇室の権威として、一時期は「皇室の家業」ではないかと思うくらいの存在であった。「連歌」と同じく「座の文芸」であったのだなと、思う。なお、ぬこ田は塗香が好きなので、極めて抹香臭い。2021/01/18
takao
2
ふむ2023/01/16
ナツ
1
随分と前にカルチャーセンターで香道の講座を受けてから興味が増してたので読んでみました! 非常に細かく香道の広まりを調べてるなぁと驚きますが、内容が知らない人名や専門的な細かいことが多くて若干読み辛かった… 後半流し読みですが、組香をベースに色々香道の楽しみ方があることは知ることができた2025/11/09
ギズモ。
0
図書館本。源氏香について読みました。2023/12/12