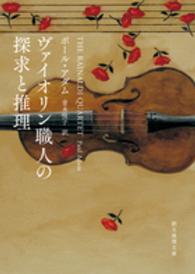出版社内容情報
鎌倉に本拠を構えた源頼朝は、物流の動脈たる街道をおさえ支配領域を拡大していく。幕府成立期に街道が果たした政治的役割を解明。「海人・野鼠」の住居といわれた鎌倉を武家政権の首都とするためには流通構造の構築が不可欠であった。源頼朝は数度の長期遠征を行い、街道をおさえ支配領域を拡大していく。東山道、奥大道という物流の動脈を基盤とした奥州平泉の平定と、二度の上洛に伴う東海道の掌握が、首都鎌倉にもたらした経済効果を明らかにし、街道の政治的意味を考える。
「動く頼朝」の視点―プロローグ/都市鎌倉と巨大都市平泉(初期の鎌倉/承久の乱後の変容/首都鎌倉の確立/北奥羽と北海道/大平泉の構造/平泉の「富の三点セット」)/東山道の政治的位置と矛盾(東山道沿いの政治矛盾/秩父平氏と大蔵合戦)/南常陸と江戸湾の掌握 富士川の合戦と金砂合戦(頼朝の挙兵/富士川の合戦―関東の西の境界を押える/金砂合戦―南常陸と江戸湾岸を押える/北関東の政治情勢)/巨大都市平泉と頼朝政権 奥州合戦の政治史(頼朝の政治―動かぬ頼朝/奥州合戦―動く頼朝)/鎌倉街道上道・東海道の整備と掌握 富士の巻狩りと二度の上洛(建久二・三年の頼朝の政治/富士巻狩りの政治的意味/二度の上洛と東海道の整備)/街道整備の進展―エピローグ
木村 茂光[キムラ シゲミツ]
1946年北海道洞爺村生まれ。1978年大阪市立大学大学院文学研究科博士課程満期退学。現在帝京大学文学部教授・東京学芸大学名誉教授。日本学術会議会員、博士(文学)※2014年5月現在【主な編著書】『日本古代・中世畠作史の研究』(校倉書房、1992年)、『日本初期中世社会の研究』(校倉書房、2006年)、『日本中世の歴史1 中世社会の成り立ち』(吉川弘文館、2009年)、『日本農業史』(編著、吉川弘文館、2010年
内容説明
鎌倉に本拠を構えた源頼朝は、数度の長期遠征を経て物流の動脈たる街道をおさえ、その支配領域を拡大していく。幕府成立期において街道が果たした政治的役割を明らかにし、鎌倉に富が集積されるにいたる過程を描く。
目次
「動く頼朝」の視点―プロローグ
都市鎌倉と巨大都市平泉
東山道の政治的位置と矛盾
南常陸と江戸湾の掌握―富士川の合戦と金砂合戦
巨大都市平泉と頼朝政権―奥州合戦の政治史
鎌倉街道上道・東海道の整備と掌握―富士の巻狩りと二度の上洛
街道整備の進展―エピローグ
著者等紹介
木村茂光[キムラシゲミツ]
1946年、北海道に生まれる。1970年、東京都立大学人文学部史学専攻卒業。1978年、大阪市立大学大学院文学研究科博士課程国史学専攻単位取得退学。現在、帝京大学文学部教授・東京学芸大学名誉教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
アメヲトコ
rbyawa