出版社内容情報
里山を創り出した古代人は、森林資源とどのように関わり生活していたのか。?木の国?日本の古代史像を、木材の利用を通して描く。持続可能な社会を目指し、いま注目されている里山。それを創り出した古代人は、森林資源といかに関わり、木材から道具を作り出し生活していたのか。用途やサイズに合った樹木の使い分け、鍬などの農具の伝播、権力者による威儀具の利用、「専業工人」の出現など、考古学の視点から解明。?木の国?日本の古代史像を、木材の利用を通して描き出す。
持続可能な社会をめざして―プロローグ/森と生きる(森と人とのかかわり〈森と集落の関係性/弥生?古墳時代の「里山」の植生を復元する/木取りから推定する/樹齢から林相を復元する/近世木地師の巡回サイクルとの類似/森が再生するペース/里山(雑木林)の創出〉以下細目略/木材の流通を復元する/木製品には何があるのか)/鍬は語る(鍬の機能を考える/鍬の系譜と伝播)/首長と王の所有物(みせびらかす器、隠匿する器/儀杖から武器へ)/うつりゆく木製品(精製木製品の変遷/専業工人の出現と展開)/弥生?古墳時代に「林業」はあったのか?―エピローグ
樋上 昇[ヒガミ ノボル]
内容説明
持続可能な社会を目指し、いま注目されている里山。それを創り出した古代人は、森林資源とどのように関わり、木材から道具を作り出し生活していたのか。“木の国”日本の古代史像を、木材の利用を通して描き出す。
目次
持続可能な社会をめざして―プロローグ
森と生きる(森と人とのかかわり;木材の流通を復元する;木製品には何があるのか)
鍬は語る(鍬の機能を考える;鍬の系譜と伝播)
首長と王の所有物(みせびらかす器、隠匿する器;儀杖から武器へ)
うつりゆく木製品(精製木製品の変遷;専業工人の出現と展開)
弥生~古墳時代に「林業」はあったのか?―エピローグ
著者等紹介
樋上昇[ヒガミノボル]
1964年、奈良県に生まれる。1987年、関西大学文学部史学・地理学科卒業。現在、(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター調査研究専門員、博士(考古学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
花林糖
こぽぞう☆
もるーのれ
どら猫さとっち
さとうしん
-

- 電子書籍
- 【電子限定おまけページつき】お願い!フ…
-

- 電子書籍
- 愛妻弁当は不倫に含まれますか?【タテヨ…
-

- 電子書籍
- アシレアン公爵の契約結婚【タテヨミ】第…
-

- 電子書籍
- 仮面に隠された愛【タテヨミ】第63話 …
-
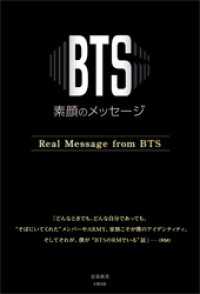
- 電子書籍
- BTS ―素顔のメッセージ―




