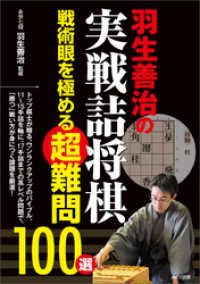内容説明
稲の品種改良を行ない、植民地での増産を推進した「帝国」日本。台湾・朝鮮などでの農学者の軌跡から、コメの新品種による植民地支配の実態を解明。現代の多国籍バイオ企業にも根づく生態学的帝国主義の歴史を、いま繙く。
目次
稲も亦大和民族なり―プロローグ
「育種報国」の光と影―「富国」と天皇
「陸羽一三二号」の伝播―賢治の米の植民地
育種技師の自民族中心主義―永井威三郎と朝鮮
蓬莱米による「緑の革命」―磯永吉と台湾
品種改良による統治―「緑の革命」の先駆的形態
日本のエコロジカル・インペリアリズム―エピローグ
著者等紹介
藤原辰史[フジハラタツシ]
1976年、北海道に生まれ、島根県で育つ。1999年、京都大学総合人間学部卒業。2002年、京都大学大学院人間・環境学研究科中途退学。京都大学人文科学研究所助手を経て、東京大学大学院農学生命科学研究科講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たらこりっぷ
9
どんな稲を東アジアの国々で育てていくか、戦前の研究者たちの活動について初めて知ることができました。肥料や農薬を生産する化学企業とのつながりにもぞっとするものを感じます。食糧増産という景気の良い言葉には警戒する必要があるのですね。それにしても、日本人が東アジアの大地で何をしてきたのか、知らないことの多さに毎回打ちのめされます。2013/01/04
アメヲトコ
6
朝鮮での永井威三郎、台湾での磯永吉らの仕事を批判的に検証しつつ、品種改良という農業技術の政治性にメスを入れた論考。技術者の心性など重要な論点が提起されていると思いますが、これは本質的には近代化の矛盾の問題であって、「稲の大東亜共栄圏」という枠組みでまとめようとすることで論証に無理が生じている箇所もままあるようにも思いました。2014/03/23
PETE
3
メンデルの法則が確立されたため、品種改良一本足打法に陥った、戦前の日本の農業政策の研究。耐冷・耐病などの属性はともかく、高収量で倒伏を防ぎ、施肥量に応じて収量が増える品種を国が推奨することの、帝国主義・資本主義との結びつきが明らかにされる。硫安などの最新の化学肥料への依存が進む割に、連作するとあまり施肥しない在来種にすら劣る新種。倒伏を少なくする短茎種は稲藁の利用価値を下げ、コメの販売益への依存を強める。そこにのし掛かる肥料購入費。台南以外の地で後回しにされる、水利・土地改良。緑の革命の失敗の先例。2022/06/13
takao
3
☆台湾、満州、朝鮮におけるコメの新品種による植民地支配(?) 日本米の改良を導入したが、肥料がかかるのが難点で普及しがたい。 どちらかと言うと、賛美されがちだが、 筆者は、生態学的帝国主義として描く。2022/01/27
ホンドテン
3
図書館で。藤原(2011)は所蔵されてない、藤原(2017)はどうもピンとこないで通読停止、でこれは読了。低食糧自給率を憂うふりして本読んで「緑の革命」なんて知ったな学生の頃・・・それを支えたIR-8やソラノが日本品種の改良とはそれだけで、新知見。過多施肥で茎ばかり育ち、あげく倒伏するなんて農業やってりゃ常識だろうが、読まなきゃ想像さえできなかった、だから憂いたふりである。書かれるどの事績も新知見の挿話で、単純に読み物として興味深い。通常なら美談なのだが、それではすまない構造的植民地問題を指摘批判する。2018/01/31