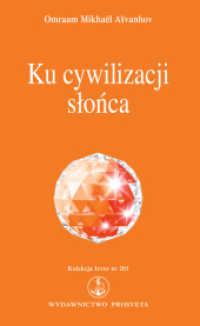内容説明
源頼朝の鎌倉入りから一五三年、不敗の歴史を誇った鎌倉幕府はなぜ呆気なく敗れたのか?政変や戦乱の経過のみならず、幕府政治の根幹を成す御家人制の質的変化に注目。定説にメスを入れ、幕府滅亡の真実に迫る。
目次
「不敗神話」の崩壊―プロローグ
幕府の職制(御家人制の成立;御家人間抗争と職制;職制の成立と制度)
特権的支配層の成立(中央集権と特権的支配層;特権的支配層の家々;特権的支配層の財力と所領経営)
鎌倉幕府の滅亡(寄合合議制の政治;地方分権と中央集権の相克;「形の如く子細なき」政治;元弘の乱)
そして動乱の彼方に―エピローグ
著者等紹介
細川重男[ホソカワシゲオ]
1962年東京都に生まれる。1987年東洋大学文学部史学科卒業。1993年立正大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程満期退学。1997年博士(文学・立正大学)。現在、國學院大學・東洋大学非常勤講師、日本史史料研究会企画部(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
akiakki
14
何冊か幕府に関する本を読んできましたが、やっと個人や家でなく、幕府の行政システムにフォーカスを当てた本に出合えました。鎌倉幕府の行政・軍事体制から、権力がどのように遷移・集中していく様子が体制視点で説明されています。体制視点だとあくまで東国武士による東国武士のための政権としてデザインされたのに、末期には西国や朝廷の揉め事まで処理せざるを得なくなり、そりゃ滅びるしかないよなと。2025/02/15
組織液
11
10年以上前の出版かつ、八十年代の卒論をもとにした本なので、後醍醐天皇の評価など所々古い印象を受けますが、全体としてはとても魅力的で新鮮にも感じる内容でした。近年は滅亡近くでもその盤石ぶりが目立つ鎌倉幕府像が主流だと思いますが、これを読むと滅亡の半世紀近く前から、幕府の命運は決定付けられていたように見えますね。いわゆる「特権的支配層」の比喩も独特で面白かったです。2025/07/18
六点
11
「将軍家とその取り巻きとの武力抗争を勝ち抜き、「天皇御謀叛を制圧した北条氏が築いた強大な権力」はどのような基盤を持ち、変遷を辿り、悲劇的な滅亡を至ったかを、平易に説いた本である。都市鎌倉に蟠踞し、「いなか、の、じけん」を対応せぬようになった中央権力は、もう一つの中央権力である「天皇」に「仕事をしないなら死んだほうが良いよね」と言わんばかりに挑戦され、御家人達は雪崩を打って見捨てたのである。当時の日本国内の移動時間を考えれば、中央集権は機能させにくく、ブロック支配が現実的だったと言えよう。2020/10/25
フランソワーズ
8
武士団、御家人制から始まり、特権的支配層にまで至る鎌倉時代の武士の性格と時代性を理解できる。次代室町時代がいかにして”用意されていたのか”ということもわかる好著。わたし的には、”鎌倉もの”でも簡単に流されがちな平頼綱や安達泰盛、長崎円喜らの御内人、「特権的支配層」についての論述がよかった。2021/05/01
リョウ
7
とりあえず幕府が成立したものの制度としては何も整っていなかった初期から、徐々に制度が整えられていく中期、そして将軍の権力を骨抜きにして執権、得宗による政治が確立されたと思ったら、代替わりによって得宗すら骨抜きにされるという権力闘争の結末が幕府の滅亡に繋がる。何より既得権益を守るために寄生虫のようにはびこった連中が自家中毒のように幕府の骨組みを蝕んでいったという評価は、今の時代も無視できない事態ではないか。2023/04/28