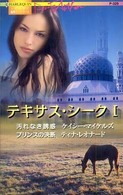出版社内容情報
満州事変から日中戦争、太平洋戦争へと突き進む政府・軍部に対し、新聞はいかに報道し、どんな論陣を張ったのか。満蒙の特殊権益をめぐる中国との対立から戦争の泥沼へとのめり込んでゆく日本。満州事変、日中戦争、太平洋戦争と続く動乱の時期、新聞は政府・軍部に対しどんな論陣を張り、いかに報道したのか。新聞紙法を始めとする法令、厳しい検閲に自由を奪われるとともに、戦争遂行へと自らの主張を転換する新聞。批判から迎合的煽動的論調への道筋を検証する。(講談社学術文庫)
第1章 自らを罪するの弁――新聞と検閲
第2章 日中対立から満州事変への道
第3章 満州事変の勃発
第4章 爆弾三勇士の真実――軍国美談はこうして作られた
第5章 国際連盟からの脱退――世界の孤児へ
第6章 5・15事件とその批判
第7章 言論抑圧による自己規制と軍民離間問題
第8章 京大滝川事件から天皇機関説事件へ
第9章 命がけの報道時代――新聞へのテロ
第10章 陸軍パンフレット事件と永田鉄山暗殺事件
第11章 2・26事件でトドメを刺された新聞
第12章 2・26事件以後
第13章 国策通信会社「同盟通信社」の誕生
第14章 日中戦争勃発
第15章 南京事件の報道
第16章 太平洋戦争への道
第17章 太平洋戦争開戦スクープ
第18章 太平洋戦争下の報道――新聞の死んだ日
前坂 俊之[マエサカ トシユキ]
著・文・その他
内容説明
満蒙の特殊権益をめぐる中国との対立から戦争の泥沼へとのめり込んでゆく日本。満州事変、日中戦争、太平洋戦争と続く動乱の時期、新聞は政府・軍部に対しどんな論陣を張り、いかに報道したのか。新聞紙法を始めとする法令、厳しい検閲に自由を奪われるとともに、戦争遂行へと自らの主張を転換する新聞。批判から迎合的煽動的論調への道筋を検証する。
目次
自らを罪するの弁―新聞と検閲
日中対立から満州事変への道
満州事変の勃発
爆弾三勇士の真実―軍国美談はこうして作られた
国際連盟からの脱退―世界の孤児へ
五・一五事件とその批判
言論抑圧による自己規制と軍民離間問題
京大滝川事件から天皇機関説事件へ
命がけの報道時代―新聞へのテロ
陸軍パンフレット事件と永田鉄山暗殺事件
二・二六事件でトドメを刺された新聞
二・二六事件以後
国策通信会社「同盟通信社」の誕生
日中戦争勃発
南京事件の報道
太平洋戦争への道
太平洋戦争開戦スクープ
太平洋戦争下の報道―新聞の死んだ日
著者等紹介
前坂俊之[マエサカトシユキ]
1943年、岡山生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。1969年、毎日新聞東京本社入社。静岡県立大学国際関係学部教授。ジャーナリズム・ITメディア論専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まると
よこしま
Satoshi
masabi
Ryuji