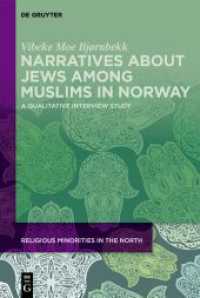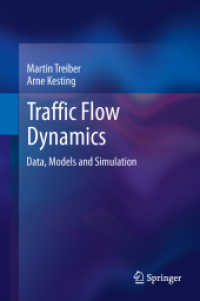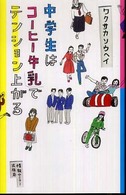内容説明
突然のペリー来航は、幕府に衝撃を与えたが、外交交渉には周到な準備をして対応した。なぜそのような戦略をもちえたか。様々な異国船への対応を検証し、海禁を維持するために奔走する幕府の姿から海防政策の本質に迫る。
目次
海防とは何か―プロローグ
ロシアとの交渉と蝦夷地問題(海禁と沿岸監視;危機のはじまりと松平定信;ロシアからの通商要求;日露関係の修復)
打払いから薪水給与へ(大津浜事件の衝撃;文政八年の異国船打払令;天保十三年の薪水給与令)
阿部正弘の苦悩(阿部正弘政権の誕生;浦賀応接の準備;嘉永二年の海防強化令;仁政論と民衆不信の相克)
形を変えて続く外国人隔離策―エピローグ
著者等紹介
上白石実[カミシライシミノル]
1964年、東京都に生まれる。1989年、東洋大学文学部史学科卒業。1993年、立教大学大学院文学研究科史学専攻修士課程中退。現在、東洋大学・立教大学・いわき明星大学非常勤講師、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
こと
4
アヘン戦争の模擬授業を行うにあたって、教材研究のために借りた。「打払令→薪水給与令」と学校では習うが、そんな簡単なことではないのだと実感。その間には様々な出来事や人の動きがあるのだと知ることができた。 模擬授業の教材研究として本を読むと、新たな発見もあり、知見が広がると感じた。2019/05/22
バルジ
3
寛政期から顕在化する「異国船」に対する幕府の施策を概観。草創期の南蛮船対策から通商や補給を求めて来航する異国船への幕府の対応の変遷が追えて面白い。打ち払いか薪水給与かで揺れ動く幕府の対応も、民衆からの異国船の隔離という一筋の線で繋がっており、幕末志士のバイブル『新論』の言説もこうした同時代的背景を基に理解出来るであろう。しかし幕府・各藩共に為政者の対外認識はバラバラで危機感が共有されていたとは見えないが、ペリー来航時までに数々の異国船対策が検討され外国使節の応対を行っていた事実は見逃してはならない。2020/08/23
nagoyan
1
優。仁政論と愚民観を往来する幕府権力の「海防」とは自国民衆に対する不信を背景とする外国人隔離政策であったという。西洋列国の武力侵略の脅威に対するものではなく、自国民衆が外国勢力と結びつくことによって支配体制が動揺することを防ぐことが「海防」であった。そのためには、本書で紹介されるように形態はさまざまあるが、要は、民衆と異国船を相互に隔離するということに主眼があった。その意味の「海防」はペリーが来航した際も実施されていた。2011/01/11