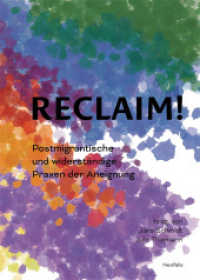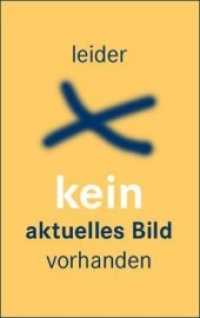内容説明
自由民権運動とは何か。「一枚の新聞の数行の文章は百万の兵卒にもまさる」「雄弁家の三寸の舌先は百万の兵に当たる」とされた言論の力に注目。幕末から大正デモクラシーまで、立憲国家の実現をめざした民権家の活動を描く。
目次
立憲政体、民権家、言論活動―プロローグ
自由民権運動とその前史(自由民権運動のめざしたもの;自由民権運動以前)
自由民権運動の展開(自由民権家の誕生;政党の結成)
自由民権運動のその後(大同団結運動と初期議会;大正デモクラシーとその後)
自由民権運動の歴史的意義―エピローグ
著者等紹介
稲田雅洋[イナダマサヒロ]
1943年、栃木県に生まれる。1972年、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了、社会学博士。現在、東京外国語大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
denz
2
権利保障と三権分立を規定した憲法を持つ国家体制という「立憲政体の早期樹立を目指して展開された運動」を民権運動として定義する。これに加えて、立憲政体樹立は将来的に行われるべきは思いつつ静観する傍観者ではなく、主体的に参加し、継続的な組織運動を武力をもちいた闘争ではなく言論によって行なうことも本書によって述べられている。また特徴的なのは、自由を回復するための明治維新観や大政奉還、民撰議院設立建白書を画期とする土佐派の民権運動史観ではなく、幕府側の立憲政体への関心を系譜に位置づけている点である。読みやすい良書。2012/05/03
屋根裏の塩
1
好みの解釈(自分は、民選議院設立建白書=板垣のわがまま=薩長閥きらい、という考え方です^^;)でしたので、さくさくっと読むことができました。いわゆる自由民権運動(建白書〜国会開設の勅諭)について、そこまでの背景とその後の流れを含みつつ、過不足なく分かりやすくまとめられていると思います。2011/05/07
りぃ
1
「大日本帝国憲法では議会は天皇の協賛機関であって~」という記述はよくある話だけど、一方で初期議会が予算案を否決したり倒閣するなど力を持っていたことは、のちの「軍部独裁」などの陰に隠れている。天皇制が「顕教/密教」に支えられていたとするなら大正デモクラシー以前に「建前/本音」が成立していたことになるか。私擬憲法と大日本帝国憲法の内容がずれていることについての民権家の反応、ということについては全く想像が及んでいなかったけれど、彼らは強かったのだなあ、と思わされた。2010/10/23
あだこ
1
最近の歴史学はかなり面白く思える。ただ単に調べました!読み変えてみました!ってだけでなく、学問的な時勢のなかである時期を位置づけて、かつそれを普遍化しようとする志向がみられる。2010/02/20