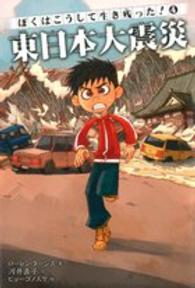内容説明
草創期の神社と政治の、不思議な関係が渦巻く平城京と平安京。神社とは何なのか。京という空間の形成から「都の神」の成立、怪異を吸いとる神社の役割まで、古代の神社の歴史をたどり、都と神社との関わりを解き明かす。
目次
京という空間と神(古代の「神」と「神社」―「かみさま」のオリジナルスタイル;都城の形成と王権祭祀;平城京と都市祭祀―神なき街創り)
「都の神」の成立(長岡、平安遷都と神社―新しい神の予兆;伊勢斎宮と賀茂斎院―国家守護の変容;都市型神社成立の意義―平野・松尾・園韓神;二十二社制の形成―神社とは何であるか)
神社と王権(怪異の収納場所としての神社;宇多王統の形成―神との関係の再生)
著者等紹介
榎村寛之[エムラヒロユキ]
1959年、大阪府に生まれる。大阪市立大学、岡山大学大学院、関西大学大学院を経て、三重県立斎宮歴史博物館学芸課長、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
19
鵺の如く正体のつかみにくい神道について、古代(平安期以前)に的を絞って分析。とは言え、宗教史というよりは政治史・都市史として読んだ方がしっくり来るのかもしれない。実際、神道の教義だの組織体系だのに関わる話はほとんど出てこず、著名な神社の立地条件や時の政権との関係性に終始する。あるいは、それこそが神道の本質なのかもしれない。明治政府が神道をいじくり回して統治の手段に利用したのにも、立派な先例があったことになる。2025/04/03
hiro6636
4
平安京成立と神々との関わりを解説。2021/10/08
わ!
2
面白い!そうなのだ、こういう歴史の捉え方もあるのですよね。歴史なのだが、人物を中心とした歴史ではない歴史…。例えばこの本であれば、平安京の成立過程と神社の形態やそこに祀られている神々の移り変わりを取り上げた一冊となっている。もちろん桓武天皇あたりは登場するのだが、メインで追いかけられるのは、都の特徴と成り立ちである。この本の説明では、それまでの平城京と比べれば、長岡京や平安京の都としての造られかたがまるで異なるというのだが、そのような説明はこの本で初めて読んだ。2018/09/18
rbyawa
2
e278、神(しん)はそもそも渡来の思想なので、日本の「かみ」の概念との融合がされたので「神神習合」と言われた時点で少し本が放り投げたくなったんですが。あと社と神は別みたいです(使い分け方が曖昧らしいけど本当に別個)、そして別に祭事の場所ってわけでもないな、と言われても…。伊勢神宮は権力の側に取り込まれて勢力を削られ、岩清水八幡宮は若宮の隆盛に嫉妬して旧宮によって略奪が行われ。みたいな歴史が語られていて正直私の手に負えるものではありませんでした。権力の真っ只中って認識だったよどっちも?! 歴史ややこしい。2014/10/05
Juichi Oda
1
神さまとはなんなのか?それは災害をもたらすものである。それは大王と豪族たちがそれぞれに信奉していたものである。御霊とはなんなのか?それは、それまでは破壊の象徴であったゴジラであって、人間と提携し宇宙怪獣キングギドラと戦ってもらうものなのである。そして神社とは、こうした怪異を収納する装置なのである。民衆エネルギーの発動に対して、権力の側が設定した吸引装置であって、政治的施設であったのだ。さらに言えば、平安京がそれまでの都と違って恒久的な存在となったのは、こうした神さまの扱いの結果のようだ。そんな本。2024/05/31
-

- 和書
- ヴェネツィア 〈下〉