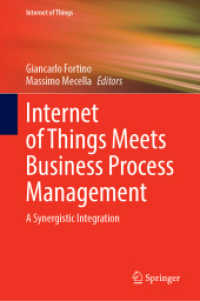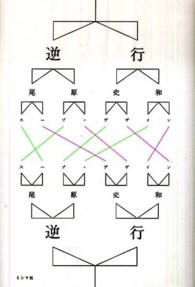内容説明
江戸時代、旅人が行き交う街道で栄えた宿場町。宿場の財政、旅籠屋で春をひさいだ飯盛女、人馬を提供した周辺の村、朝鮮通信使への豪華接待など、知られざる宿場運営のシステムとは。宿場を支えた人びとの姿が、いま蘇る。
目次
五街道と脇往還―プロローグ
宿場とその運営
宿場の陰影―飯盛女の生活
宿場を支えた村々
外国人の来日と村々
宿駅制度の終焉―エピローグ
著者等紹介
宇佐美ミサ子[ウサミミサコ]
1930年、神奈川県小田原市に生まれる。1953年、法政大学法学部卒業。1989年、法政大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得修了。文学博士。現在、法政大学史学会評議員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ちょんまげ
3
江戸幕府は参勤交代に使う街道を作りました。この道は余りにも長いので、途中に休憩所(宿場)がいくつもあります。大名達は朝から夕方まで歩き、ここで一泊してから次の宿場へ向かいます。これは幕府の政策ですが、なんと、宿場の運営や街道の清掃などは全て庶民にやらせていたそうな。幕府にはお金も人材もなかったんですね。そのため、裏で庶民が売春して大名からお金稼いでも、幕府は文句言えない。だってその収益の一部は幕府に献上されるから。たまにお偉い様も泊まるから幕府は売春禁止したかったが叶わず。こんな話です。2016/11/30
T F
1
江戸時代に幕府が整備した宿場は、地元民には結構な負担だったようだ。飯炊き女というのも、売春とからんで、なかば人身売買に近い。2019/10/27
Tatsuo Mizouchi
1
☆☆☆ 小田原宿の話が中心ではあるが、、、 宿場は自然発生的にできたものではなく、 幕府が作らせたものであり、すべて幕府の指示。 公儀のため、助郷制度など地元にとっては負担でしかない。 その補てんとして飯盛女を認めたのですね。2017/04/10
じょういち
1
筆者もあとがきで述べているが、タイトルは『小田原宿の歴史概略』とかがいいのではないだろうか。『宿場の日本史』というわりに、他の宿場の話が『夜明け前』の引用ばかりとは悲しい。飯盛女については、筆者の別の著作の方が詳しい。2017/01/24
wang
1
江戸時代の諸街道にもうけられた宿場の実体。宿場は具体的にどのような役割を担ったのか?その経済、建物、役人は?など主に小田原宿の事例を中心に記す。個別の費用や食事内容など細部に及ぶ記述は実際の宿場を想像する助けになる。飯盛女、助郷などの問題や朝鮮通信使への取り扱いなど多岐にわたる問題もとりあげる。特に幕末維新後の往来を支えた皆同周辺の村々の疲弊など大河ドラマでは描かれないない歴史を支えた民衆の存在も。2011/08/12