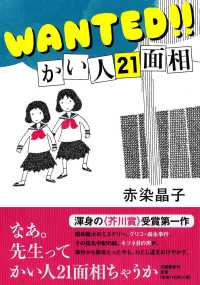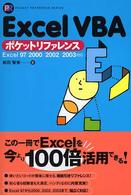出版社内容情報
従来、京都上層の民衆集団である「町衆」の代表的存在で、都市経済を支える金融業者と位置づけられてきた土倉・酒屋。この定説を検証し、『蜷川家文書』『八瀬童子会文書』などの史料から土倉・酒屋とみなされてきた者たちの本来の身分を見出し、権力とのつながりを解き明かす。応仁・文明の乱前後の実態分析から、京都の社会構造を再検討する。
内容説明
従来、京都上層の民衆集団である「町衆」の代表的存在で、都市経済を支える金融業者と位置づけられてきた土倉・酒屋。この定説を検証し、『蜷川家文書』『八瀬童子会文書』などの史料から土倉・酒屋とみなされてきた者たちの本来の身分を見出し、権力とのつながりを解き明かす。応仁・文明の乱前後の実態分析から、京都の社会構造を再検討する。
目次
中世後期の社会構造と土倉・酒屋
第1部 京都の「土倉」の実態(戦国期京都の「土倉」と大森一族―天文一五年の分一徳政令史料の再検討;応仁・文明の乱以前の土倉の存在形態;中世の「土倉」に関する解釈の淵源;室町時代の東寺執行方公人―稲荷祭礼東寺中門御供の担い手の変化)
第2部 京都の「酒屋」と室町幕府(神宮御倉と室町幕府;禁裏御倉と室町幕府;応仁・文明の乱後の酒屋・土倉と「武家被官」;戦国期の蔵人所御蔵と洛中の住居;中世の節供―祇園社を中心に;真継家と配下の鋳物師―鋳物師田中家と「仁左衛門」の登場をめぐって)
中世後期の京都研究の問題と展望
著者等紹介
酒匂由紀子[サカワユキコ]
2005年立命館大学文学部史学科日本史学専攻卒業。2007年立命館大学大学院文学研究科日本史専修博士前期課程修了。近江八幡市史編纂室史料調査員を経て、2016年立命館大学大学院文学研究科人文学専攻日本史専修博士後期課程修了。枚方市市史資料室市史資料専門員を経て、現在、立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
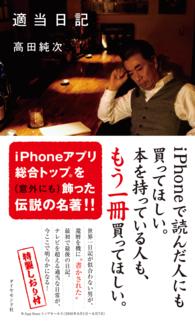
- 電子書籍
- 適当日記