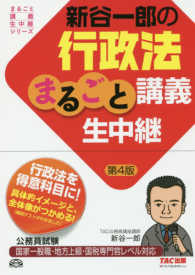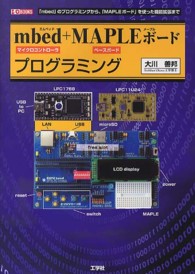内容説明
音楽プレーヤー、読書端末、財布としての機能まで有し、日常に欠かせないものとなった「ケータイ」は、私たちのコミュニケーションや社会の変化にどのように関わっているのか。メディア論やコミュニケーション論の知見から「社会的存在としてのケータイ」を読み解き、現代社会の一側面にせまる。
目次
ケータイから学ぶということ
「ケータイ」の誕生
ケータイの多機能化をめぐって
若者とケータイ・メール文化
ケータイに映る「わたし」
ケータイと家族
子ども・学校・ケータイ
都市空間、ネット空間とケータイ
ケータイと監視社会
ケータイの流行と「モビリティ」の変容
モバイル社会の多様性―韓国、フィンランド、ケニア
モバイル・メディア社会の未来を考える
著者等紹介
岡田朋之[オカダトモユキ]
関西大学総合情報学部教授。専攻:メディア論、文化社会学
松田美佐[マツダミサ]
中央大学文学部教授。専攻:コミュニケーション/メディア論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MasakiZACKY
1
ケータイを12章にもなる様々な側面から眺め「社会とケータイ」について述べた一冊。僕の学部の先生も執筆者の一人なので手にとったが、そうでなかったら読んでないとは愚かな自分である。この軽めの本の中に、ケータイの社会学的な論考が凝縮されている。移動体メディア関連年表や巻末資料も極上。『ケータイ学入門』のリニューアルとは言っても、この激動の10年間を含めた本著はやはり別物に。特に「若者とケータイ・メール文化」「「ケータイと家族」「子ども・学校・ケータイ」は興味深く、さらに10年後のリニューアルが今から期待である。2012/10/24
がっちゃん
0
補助資料として。第八章のテーマ、都市空間とケータイに興味あり。2016/06/13
-
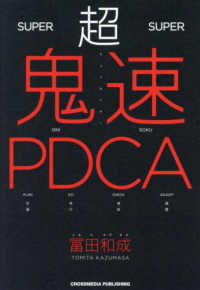
- 和書
- 超鬼速PDCA