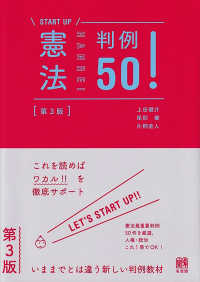内容説明
家族をめぐる最新の統計、重要な法律の制定や改正、注目すべき裁判例に目配りした、充実の第2版。
目次
1 夫婦の絆と結婚のしくみ(結婚をするために;結婚をすると;夫婦の姓と戸籍;夫婦をやめるとき;夫婦の一方が死んだら)
2 結婚を超えて(届出をしない夫婦;同性のカップル;国際結婚―国境を超えた愛;ドメスティック・バイオレンス;夫婦の性的自立 ほか)
著者等紹介
棚村政行[タナムラマサユキ]
1953年生まれ。1977年早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院法務研究科・法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たこ焼き
6
結婚する前から所有する財産はその人特有の財産になる。夫婦が共働きで稼いだ場合、または片方働きでもその共有不動産や動産は一方の名義であっても実質共有財産(特に不動産)とみなされることもある。その場合は共同生活への寄与割合を算出される。離婚における財産分与は分与を請求するときに一方が有責があるかどうかの慰謝料請求とは性質を異にするもの。有責配偶者からの離婚請求は認められることがある。子供がいないときは遺留分は1/3。2025/09/06
ペールエール
0
「家族に法律は入らず」 家族間のもめごとは基本的に当事者同士の話し合いで解決すべきであり、立法という類のもので裁くべきではない。 というのが昔からの一般論であった。 しかし、近年の家族内での紛争の増加などを考えると、立法による仲介・制裁措置を求めるのも自然であろう。 「倫理的な問題」に、法律を適用させるのは非常に難しい。 しかしその中でもたくさんの学説があるのが分かった。 法的構成などももっと勉強していきたい。2012/11/30
みうら
0
2006年のデータ。かなりの改正が入っており今と異なる部分も多くあるが、逆に改正が入ったところは、やはり当時からも問題だったのだと再確認できる。教科書というよりは読み物に近い。2024/11/13
-
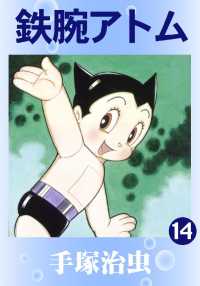
- 電子書籍
- 鉄腕アトム - 14巻
-
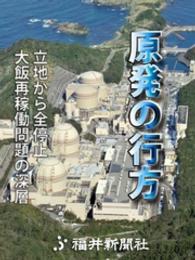
- 電子書籍
- 「原発の行方」 立地から全停止 大飯再…