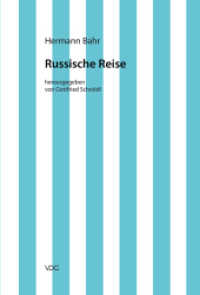出版社内容情報
松沢 裕作[マツザワ ユウサク]
著・文・その他
内容説明
現代日本社会の原型がここに。近世の身分制社会が崩れる19世紀後半から、明治維新を挟んで、第一次世界大戦の頃までの日本社会を、さまざまな社会集団が市場とどうかかわっているかに注目して描き出す。
目次
社会史とは何か?日本の近代とは何か?
近世社会の基本構造―領主・村・町
近世社会の解体(一)―廃藩置県と戸籍法
近世社会の解体(二)―地租改正と地方制度の制定
文明開化・民権運動・民衆運動―移行期社会の摩擦
景気循環と近代工業―資本主義の時代の到来
小農経営と農村社会―農家とその社会集団
女工と繊維産業―「家」から工場へ
商工業者と同業組合―家業としての商工業とその集団
職工と都市雑業層―「家」なき働き手と擬制的な「家」〔ほか〕
著者等紹介
松沢裕作[マツザワユウサク]
1976年、東京都に生まれる。1999年、東京大学文学部卒業。2002年同大学院人文社会系研究科博士課程中途退学。東京大学史料編纂所助教、専修大学経済学部准教授、慶應義塾大学経済学部准教授を経て、2020年より現職。現在、慶應義塾大学経済学部教授。専門は、日本近代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
15
ストーリー性のある政治史や、華やかな文化史に比べると地味な印象の強い社会史についての概説。経済学部の講義をもとにしているので、一章ごとの構成がしっかりしていて短くても読み応えがある。近世の権力を背景にした身分制集団から近代の社会集団への変化というのが、地方自治、農業、工業、教育、メディアなどの各テーマから整理されている。2023/05/02
YN
1
明治維新期以降、第一次世界大戦までの間に日本社会がどう変容したかを、様々な視点から描く。家を中心とした社会は、擬似的な家のようなものを包括しつつも、根底にあるOSが大きく変わったために異なるゲームが出現した。2023/12/30
Ra
1
個人間をつなぐ「社会集団」と社会集団間をつなぐ「市場」を2軸に日本近代社会を描写.近世は,個人は「家」を通じて身分的社会集団(筆者は「袋」と表現)にまとめられ,国家から当該集団を通じて賦課される役を果たす.このうち「町」は非計画的に断行された戸籍法と廃藩置県,「村」は地租改正と明治の大合併により解体.これらの解体は,集団からの個人の解放と,市場の再定位(政治内→公私二元下の私的領域)を促す.以降,社会集団は再構成されるが「抜け駆け可能」であり,政治は市場の円滑化のための社会資本整備(=利益誘導)に傾倒.2023/03/19
Go Extreme
1
社会史・日本の近代 近世社会の基本構造─領主・村・町 近世社会の解体─廃藩置県と地方制度の制定 文明開化・民権運動・民衆運動─移行期社会 景気循環と近代工業─資本主義の時代到来 小農経営と農村社会─農家とその社会集団 女工と繊維産業─家から工場へ 商工業者と同業組合─商工業とその集団 職工と都市雑業層─家なき働き手と擬制的な家 都市の姿─有産者の結合と都市計画 教育と立身出世─家の世界からの離脱 メディアの変化 政治の役割 労働組合と初期社会主義─個人→社会の問題 日露戦後の社会 日本近代社会の構造と展望2022/05/21
太郎
0
近世的身分秩序から近代へ移行し、その段階で家が解体されていく過程がわかる本。 個人的には1から4章、6章がとても面白かった。 とりあえず、『民衆暴力』再読と、『自由民権運動』の読了を目指したい。2025/07/11
-

- 電子書籍
- 公女殿下の家庭教師【ノベル分冊版】 2…