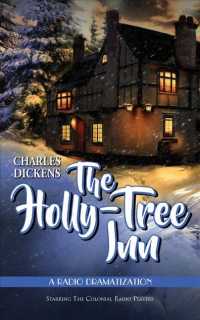出版社内容情報
東京大学での講義をもとにした書き下ろし教科書。「いじめ」「愛国心」「○○化する社会」など,社会的な話題をどう考えると社会学になるのか。「等価機能主義」に軸足をおき「問題がどのような意味で問題なのか」を社会学理論を背景に吟味し,社会問題について考える道筋を示していく。
内容説明
誰でもお手軽に社会批評を嗜む時代に、社会学はいかにして専門知としての矜持を持ち続けられるのか?当代きっての理論社会学者が東京大学でおこなった授業をもとにまとめた、講義形式で身につける社会学の「規準」。
目次
1 社会学はなんでもありなのか?
2 社会学の「下ごしらえ」
3 等価機能主義の理論と方法1―因果的説明と機能的説明
4 等価機能主義の理論と方法2―等価機能主義のプログラム
5 「他でありえた」可能性と「スパンドレルのパングロス風パラダイム」
6 中間考察・等価機能主義の方法規準―なんの比較か?
7 等価機能主義の/からの問題1―社会理論の飽和と社会問題の社会学
8 等価機能主義の/からの問題2―民間社会学としての「社会解体論」
9 等価機能主義を実践する―メディア論とフィールドワーク
10 復習編―次のステップに進むために
著者等紹介
北田暁大[キタダアキヒロ]
東京大学大学院情報学環教授。1971年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程退学後、同大助手、筑波大学社会学系講師、東京大学社会情報研究所助教授、同大学大学院情報学環准教授等を経て現職。博士(社会情報学)。専門は理論社会学、メディア史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひばりん
ぷほは
takao
かとたか
pankashi
-

- 電子書籍
- 最近