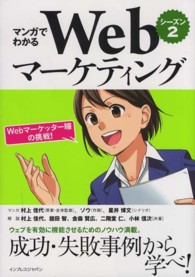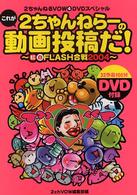内容説明
幕末から明治初年にかけて締結された「不平等条約」は、いかに改正されたか。日本は、領事裁判制度撤廃の国際的合意をかちとりながら、それに反発する政府内外のナショナリズムによって、繰り返し条約改正交渉の挫折を余儀なくされた。明治初年の混迷を経て、本格的に改正交渉を行うようになった寺島外務卿と井上外務卿・外相期を中心に、条約改正を、法権回復交渉の停滞・前進としてではなく、行政権回復交渉の挫折、その結果としての法権回復への跳躍ととらえ、政治外交史の観点から解明する。
目次
研究史と前史、視覚
第1部 行政における主権回復の試み(寺島宗則外務卿と税関行政;井上馨外務卿と警察行政)
第2部 法権回復への跳躍(条約改正予備会議;会議の間―日本の台頭と最後の暫定協定構想;条約改正会議―法権回復への国際的合意と国内対立)
総括と展望
著者等紹介
五百旗頭薫[イオキベカオル]
1974年、兵庫県に生まれる。1996年、東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手、東京都立大学法学部助教授、首都大学東京法学系准教授などを経て、東京大学社会科学研究所准教授(日本政治外交史専攻)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ぼのまり
4
幕末から明治に結ばされた不平等条約を改正するために、欧米先進各国との駆け引き、交渉、平行して行なわれる日清条約改正の交渉の記録、そして内政としての方針、思惑の違いの調整などが詳細に記述されている。現在の日本の状況を照らし合わせてみると、類似する部分が多い。一対一の国同士の交渉だけでも、かなり骨の折れる作業であるが、グローバル社会では更に複雑化するのは目に見えている。戦後復興を考えた場合、「棚上げ」はひとつの戦略として有効だったようにも思う。今は?今一度考えてみたい。2013/07/16
メルセ・ひすい
3
14-72 赤76必読書 ★5 ペリー米国不沈空母化・標的日本開国! 対欧米(生き血ススリの植民地主義達人国と締結した不平等条約をモガキナガラ改正した経緯。その軌跡とは…交渉のトップ寺島・井上外務卿=外務大臣の在任期1872~1887年。この間10年、明治元年の混迷を経て我国が本格的な条約改正交渉を開始した時代。その根幹にカカワル領事裁判制度の撤廃に対する国際的合意ゲット。しかし、国内外、近世ナショナリズムが世界の雰囲気を覆いつくしていた。「不平等条約」の運用をめぐる小さな紛争の日々が始まる。2011/03/21
文明
2
行政権回復交渉とその挫折、その結果としての法権回復への跳躍として条約改正を描く面白い本。行政の意義、本国政府との外交関係、日清交渉との連動という観点も含まれている。時に個別の事例の事実発見に汲々とすることがあっても、政治史は最終的には国家論でなければならないことを再確認した。2024/08/28
メルセ・ひすい
1
14-832011/04/14
nagoyan
1
優。本書は日本側の条約改正に対する強い動機づけとして従来注目されていなかった「行政権回復」とする。寺島や前期・井上馨による行政権回復を主眼とした条約改正交渉がいかに挫折せざるをえなかったかを描き、その結果、より包括的で困難な「法権回復」を目指す「跳躍」をするに至った力学をみつめる。行政(税関・防疫)規則の制定・執行すら外国領事の掣肘を受ける現場の不満をばねとし改正交渉を進める。しかし、部分的な取引は複雑・困難となり、結局内地開放と法権回復を一括解決する形でしか条約改正案は成立し得なかった。これも挫折する。2011/01/17
-

- 電子書籍
- このSを、見よ! クピドの悪戯(2) …