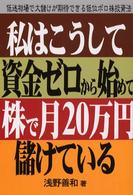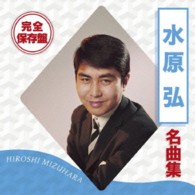出版社内容情報
身近になりつつも,未知の部分が大きいAI。そんなAIが社会に与えるインパクトに,法はどう向き合うのか。公法・私法・基礎法研究者と情報技術の専門家がタッグを組み,座談会形式で考える。論究ジュリストでの好評連載をまとめた待望の1冊。
目次
第1章 テクノロジーと法の対話
第2章 データの流通取引―主体と利活用
第3章 契約と取引の未来―スマートコントラクトとブロックチェーン
第4章 医療支援
第5章 専門家責任
第6章 著作権
第7章 代替性―AI・ロボットは労働を代替するか?
第8章 サイバーセキュリティ
第9章 フェイクとリアル―個人と情報のアイデンティフィケーション
第10章 これからのAIと社会と法―パラダイムシフトは起きるか?
著者等紹介
宍戸常寿[シシドジョウジ]
東京大学教授
大屋雄裕[オオヤタケヒロ]
慶應義塾大学教授
小塚荘一郎[コズカソウイチロウ]
学習院大学教授
佐藤一郎[サトウイチロウ]
国立情報学研究所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shikada
15
AIは社会と法にどんな影響を及ぼすか、大学教授たちが対談した一冊。著作権の話が興味深かった。現状では、AIが作品を作っても、AI自体に著作権は属しない。猿がスマホで写真を撮っても、猿に著作権が属しないのと同じ。ただ、AIの進化はめざましく、人間と遜色ない絵や文章を作れるようになってきている。AIが作った場合著作権で保護されないのであれば、AIに作品を作らせて「私(人間)が作りました」と嘘を言って著作権の保護を受ける「僭称問題」が発生し得る。2022/12/27
Bevel
2
「専門家責任」の話が面白かった。医療行為は「過失責任」つまり、身体状況の悪化を前提としコントロールできるかぎりで理由のある判断をしなければ罰せられる。AIをスクリーニングのために用いる場合、医者の総体的な能力=可能性を増強しているのだから、スクリーニングで見過ごされるリスクは患者に負わせるのでよい。またこのとき、AIの性能の良し悪しはそれほど問題にならないが、AIの判断の信頼性に関する情報(例えば偽陽性、偽陰性の割合)は知らされてないといけない。患者がAIを使って医者に反論しうるという指摘も面白かった。2024/11/23
げんさん
0
製造物責任法がある以上完全な自動運転車が世に出るのはまだまだ先か。宍戸常寿先生が「ヨルムンガンド」を読んでいるなんて2020/11/03
まさやん510
0
AIが社会や法の各領域にどのような影響を及ぼすのか、AI技術の現在地がどのようなレベルであり、どのような課題があるのかについて幅広く触れることができた。 メモ ・AIに対して過度な期待やファンタジーなイメージを持つことは適当ではない ・個人情報保護法の保護法益は「漠然とした不安の緩和」。どのような条件さえ満たせば安心して個人情報を使えるのかを明らかにする「情報利用促進法」2020/09/20
-
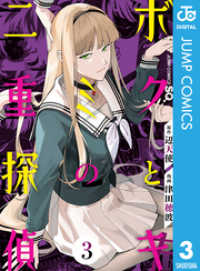
- 電子書籍
- ボクとキミの二重探偵 3 ジャンプコミ…