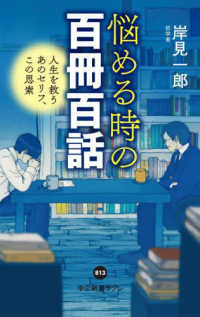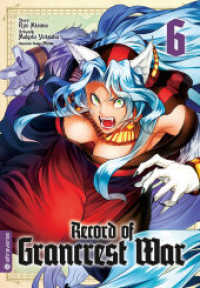内容説明
最高裁判決はどう作られ、どう読むのか。事件の紛争解決と新たな法解釈・規範創造という二つの要請の間で苦心する最高裁の判決作成過程を、著者が担当した事件の審議で感じたことや、判決論理に込められた意味の読み解きを通して熱く語る。
目次
第1部 最高裁判所判事の日常(最高裁判所での生活;事件の審理を通して感じたこと;自由時間の過し方―激務への対処法)
第2部 印象に残る事件と判決(大法廷の事件から;第三小法廷での審議事件から;その他の審議事件の感想など;最高裁判例の果たすべき役割)
第3部 これからの学者、法曹、学生に対するメッセージ(学者と裁判官の間;学者の論文、判例評釈について;法科大学院と民法担当の研究者教員;民法担当教員と実務家教員との交流・協働;法曹へのメッセージ;法科大学院制度について;法科大学院の学生に対するメッセージ)
著者等紹介
奥田昌道[オクダマサミチ]
1932(昭和7)年生まれ。1955年京都大学法学部卒業。1970年京都大学法学部教授。1996年鈴鹿国際大学国際関係学部教授。1999年最高裁判所判事。2002年同志社大学法学部特別客員教授。2004年同志社大学大学院司法研究科特別客員教授。日本学士院会員。現在、京都大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。