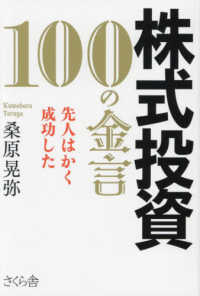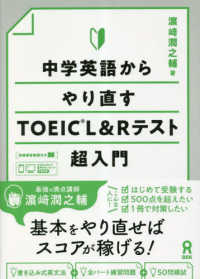出版社内容情報
畿内の様相を古墳時代から古代にかけて通観する「講座 畿内の古代学」シリーズ第5巻(全6巻)。
「祭祀」「仏教」「畿内の文化」という三本の柱を軸に、宗教・文化的側面における畿内地域の先進性に迫る。
内容説明
第5巻では、政治的中心であった「畿内地域」がいつ、どのように文化的中心としての側面も獲得したのかについて、この地域の文化・イデオロギーの構成要素や、他地域との特徴の差などを問題意識として考察していく。
目次
序論
第1章 祭祀(聖水祭祀;神祇祭祀と畿内;疫神と御霊;二十二社制の形成)
第2章 仏教(王宮と王都の仏教;畿内の飛鳥・白鳳寺院;行基建立の四十九院と知識;畿内国分寺の諸相;平安京と山林寺院;円宗寺結縁潅頂―院政期御願寺仏事の変転)
第3章 畿内の文化(古墳時代生活様式の先進性;暦と漏刻;仏像製作と畿内)
著者等紹介
広瀬和雄[ヒロセカズオ]
1947年京都市生まれ。大阪府教育委員会、大阪府立弥生文化博物館勤務ののち、奈良女子大学大学院教授。現在、国立歴史民俗博物館名誉教授・総合研究大学院大学名誉教授
山中章[ヤマナカアキラ]
1948年京都市生まれ。現在、三重大学名誉教授
吉川真司[ヨシカワシンジ]
1960年奈良県生まれ。京都大学助手、同助教授(准教授)、同教授を経て、京都大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
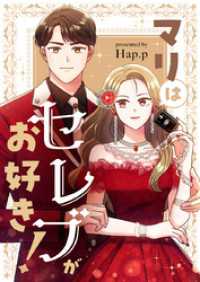
- 電子書籍
- マリはセレブがお好き!【タテヨミ】第5…