出版社内容情報
考古学者が漆の分析の枠組みとその成果を理解できるものとする。そのためには分析の結果だけではなく、どれくらいの分析試料で何がどこまでわかるかを具体的な事例の紹介を通じて理解できるものとする。理化学分析の有効性を考古学の世界に広く周知する。漆が漆器だけでなく、補修材、胎の製作技術など、自然資源の有用化としてさまざまなモノ・現象にかかわりをもつということを示す一書。
内容説明
漆の分析から縄文社会の実像に迫る。考古学・植物学・応用有機化学などの多角的な視点から縄文時代の「資源」としての漆利用技術を分析し、歴史的背景を解き明かす。
目次
序章 「縄文の漆工芸」と社会
第1章 ウルシの性質と有機化学分析の実際(ウルシという植物の特性;漆の科学分析の歴史とその概略)
第2章 縄文漆の理化学的分析(縄文のウルシ利用と科学分析;漆膜の構造からみえる縄文の漆工技術;漆の産地と年代の探究;漆に関わる材料の分析)
第3章 漆器の製作技術の解明(木胎製作と磨製石斧;櫛の製作;接着剤としての漆―東村山市下宅部遺跡出土資料の事例)
第4章 漆と縄文社会(ウルシ利用の人類史;前期の集落形成と漆工芸の展開;中期集落と漆工芸の関係―デーノタメ遺跡を中心とした漆利用;漆文化の地域性―前期を中心に;縄文時代後晩期の漆器と容器間関係;漆製品の埋葬と社会―カリンバ遺跡)
著者等紹介
阿部芳郎[アベヨシロウ]
1959年生。明治大学文学研究科史学博士課程単位取得後退学。博士(史学)。現在、明治大学文学部教授。明治大学資源利用研究クラスター代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
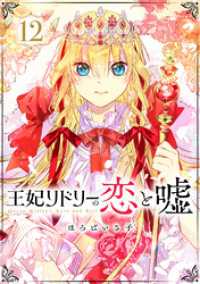
- 電子書籍
- 王妃リドリーの恋と嘘 分冊版 12 C…
-

- 洋書電子書籍
- Jake the Fake Goes …






