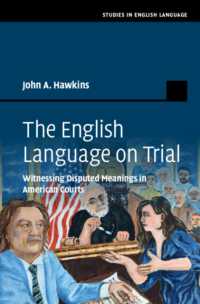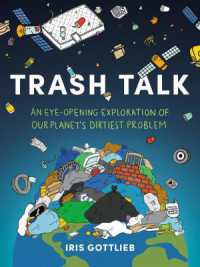内容説明
身近で、使うことが当たり前になっている寝具たち。だが、それほど身近な存在でありながらわれわれの祖先がいつ頃からどのように寝具を使い始めたのかを知る人も思い馳せる人も少ない。日本人と寝具そして寝所との関係をまとめた名著を復刊!
目次
第1章 上古・上代の寝所と寝具(原始住居と寝室;上古・上代のタタミとフスマ;トコという言葉の問題 ほか)
第2章 平安・鎌倉時代の寝室と寝具(寝殿造の構造;塗篭の役割;御帳と帳台 ほか)
第3章 室町時代から現代まで(中世住宅の寝室と帳台構;室町時代の就寝風俗;安土桃山時代の寝具 ほか)
著者等紹介
小川光暘[オガワコウヨウ]
1926年奈良に生まれる。同志社大学文学部(文化史学専攻)卒。同志社大学文学部および同大学院の教授として日本の美術史、寝具史を研究した。1995年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くらーく
1
この時期、羽毛布団に入るのが幸せです。振り返ってみれば、子供の頃は綿の重い布団で、敷布団は薄っぺら。朝起きれば、周りに霜が降りていた。今は随分と良くなったなあ、と。祖母は布団に対しては本当に厳しくて、足で踏んだだけでグーで殴られる程でした。大切な家財道具だったのでしょうな。いつから、布団で寝られるようになったのだろう?いつから、こんなに快適な寝具になったのだろう、と思って、図書館で見つけたのがこの本。まあ、それなりに興味は満たされるのだけど、あまり情報が残っていないようですね。2022/12/17