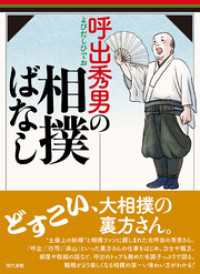内容説明
過去を考える視点の多様性と現代における貝塚の意義を考える。膨大な資料をもとに考察する最先端の貝塚研究。姥山貝塚・古作貝塚・園生貝塚・加曽利貝塚・千葉貝塚(群)など代表的な巨大貝塚の学史の再検討。貝塚遺跡の保存と整備・活用の第一人者と考える座談会。
目次
第1章 貝塚研究の歩み(貝塚を発掘した人々とその研究;大規模開発と貝塚研究)
第2章 東京湾貝塚の学史と新展開(姥山貝塚「接続溝第1号竪穴(住居址)遺骸」の死体検案
加曽利貝塚の形成過程と集落構造―調査記録の再検討と縄文集落研究の課題
貝塚解題―船橋市古作貝塚を例として
園生貝塚の研究史と後晩期の大型貝塚
千葉貝塚(貝塚町貝塚群)と縄紋式社会研究)
第3章 最先端の貝塚研究と縄文社会論(大型貝塚形成の背景をさぐる;東京湾沿岸における縄文時代人骨に見られる古病理学的研究について―千葉県市川市姥山貝塚出土例を中心にして;大型貝塚調査から見えてきた縄文時代の装身具の実態と貝材利用;微小小貝類からみた東京湾沿岸の巨大貝塚の時代)
第4章 座談会 巨大貝塚はどう守られたのか
著者等紹介
阿部芳郎[アベヨシロウ]
1959年生。明治大学文学部教授。明治大学日本先史文化研究所所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。