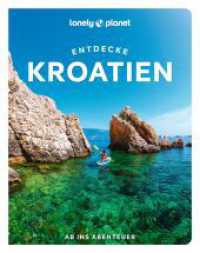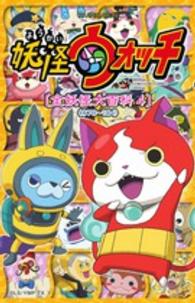内容説明
横穴墓から復元する後期古墳社会。東アジア世界における日本の横穴墓制の形成と各地域における展開を把握し、群集墳としての横穴墓の性格を検討する。
目次
序章 横穴墓研究の課題と研究の視角
第1章 横穴墓の名称と研究史(横穴墓の名称;横穴墓の被葬者と性格論)
第2章 横穴墓の諸相(群集墳としての横穴墓;東国横穴墓の型式と交流;東国展開期横穴墓の諸相)
第3章 横穴墓出土遺物の検討(東国における群集墳出土の鉄鏃;横穴墓出土の農工具)
第4章 横穴墓の形成と展開(東アジア世界における横穴墓制の形成;各地における横穴墓の展開)
結論
著者等紹介
池上悟[イケガミサトル]
1950年鳥取県に生まれる。1977年立正大学大学院修士課程修了。現職、立正大学文学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
綱渡鳥
0
日本の横穴墓研究の第一人者である著者。得意の学史から丁寧に解きほぐして、「横穴墓」という名称がどう変わっていったのかも解説。全国津々浦々に所在する古墳の総数は20万基とも言われ、そのうち3・4万基は横穴墓だといいます。その数からして横穴墓研究の重要性がわかろうというもの。まずは被葬者像から始まって、高塚古墳も含めた群集墳の中での位置付け、形式の伝播ルート、副葬品の農工具や、文化発生の地である中国での状況など多くの視角から横穴墓を分析。そこから解き明かされる結論は意外なもの。ぜひ一読をオススメする。2019/02/07