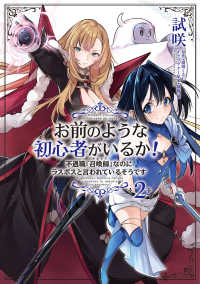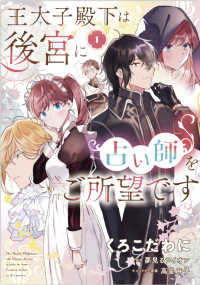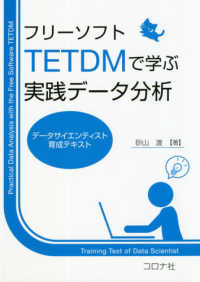内容説明
豊かな自然と付き合う中で、身体を使って暮らしてきたはずの日本人。解剖学者・養老孟司とナチュラリストのC.W.ニコルが、現代人の自然欠乏による「身体感覚の衰え」を語る。
目次
第1章 森と川と海のこと
第2章 食べること、住まうこと
第3章 子どもたちと教育のこと
第4章 虫のこと、動物のこと
第5章 五感のこと、意識のこと
第6章 聞くこと、話すこと
第7章 これからの日本のこと
著者等紹介
養老孟司[ヨウロウタケシ] [Nicol,C.W.]
1937年神奈川県鎌倉市生まれ。解剖学者。東京大学名誉教授。1962年に東京大学医学部を卒業。1981年、東京大学医学部教授に就任。1995年に東京大学を退官。脳科学や人間の身体に関するテーマをはじめ、幅広い執筆活動を行う。昆虫研究でも知られ、福島県須賀川市の科学館「ムシテックワールド」の館長を務める
ニコル,C.W.[ニコル,C.W.]
1940年英国ウェールズ生まれ。作家、環境保護活動家、探検家。カナダ水産調査局主任技官、エチオピア・シミエン山岳国立公園長などを歴任後、1980年長野県に居を定める。1986年、荒れ果てた里山を購入し『アファンの森』と名付け、森の再生活動を始める。2002年「一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団」を設立し、理事長となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
111
限界集落をかわいそうと言うが、年寄りが暮らせるほどにいい所。都会は変化がないから。明るさも一定、泥臭さがなくて、賢いな人ばかりになり不自然。表情も乏しい。人間の顔は鼻と口が平らでしょう。嗅覚が退化して顔色を窺うようになり、社会生活をし始めて色を感じる細胞が3つに増えた。視覚に頼りすぎ、答えを求めすぎている。もっと感覚を研ぎ澄まし、自然や身体を感じ、自分を取り戻してほしい。周りに合わせすぎて自分を見失う。悲しいと思いませんか。世間から少し距離を置いて、常識と違う判断をしてみる。そんな生き方をしてみませんか。2019/11/13
ほう
24
黒姫高原にアファンの森を創設されて、自然環境の大事さを発信し続けたC・Wニコルさんと、解剖学者でありながら昆虫研究も深く関わっている養老孟司さんの対談集である。我々が忘れているか、または捨て置いている事柄がお二人の言葉で呼び起こされる。ボタン一つで暮らしを成り立たせている私たちの暮らしは、まことに脆いとしか言いようがない。2023/01/03
Sakie
18
2020年に亡くなったC.W.ニコル氏と養老先生の対談、2014年。ニコル氏はアファンの森をつくったり馬を使役したり学校創設に関わったりと活動の幅広く、養老先生も保育園の理事長を引き受けたりされているので、日本の未来を想って、日本の自然や子供のために尽力している共通点がある。"We have to be gardeners"。感覚は違いを発見するもの。意識は同じを見つけるもの。どちらに傾きすぎても生きづらいけれど、感覚の世界の奥深さを忘れては人は生きられないのだよという大切なメッセージ。広い土地欲しい。2022/09/03
ふじ
17
過激派ニコル氏と自然大好き、理系養老先生の対談。様々のメンタルの不調を『自然欠乏症』としていて斬新。他にも英語は客観的、日本語はどうしても主観的な文章になりがち、とか、若者のために老人はさっさと滅びろ(笑)とか。学校の役目の変遷(今は知識教育は自宅でも可能、それ位意外が求められる)とか。対談から見える視点が刺激的。でもニコル氏は現代(特に技術進歩)に否定的すぎで好みでなかった。ITは悪で自然は善なんて簡単な話はないと思う。2017/03/18
Kikuyo
15
自然が足りないと世界が半分になる。人間世界だけで生活してるとせますぎる。 自然不足と言われて久しいが、その傾向は加速して、さまざまなおかしな人間を生産してるようにも思う。2022/11/11