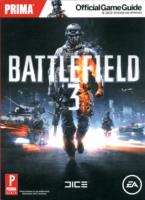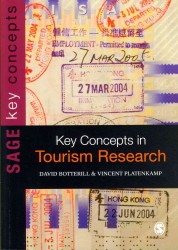内容説明
深刻化する野生動物と人間の遭遇。保護か、捕獲か、駆除か。解決の糸口はあるのか?第一人者による、まったなしの緊急出版!
目次
第1章 平成のシシ荒れ(動き出した動物たち;受け身なクマ;自然変容説から環境適応説へ)
第2章 生息域拡大期の現実(人喰いグマはいるのか;被害の二重構造;むき出しの都市)
第3章 近世の相克「シシ荒れ」森の消長と野生動物(生きるための闘い;旧弘前藩領での出来事;動く森の片隅で)
第4章 狩猟の公共性(接近する被害現場―バリア・リーフ構造の崩壊;狩猟と農耕;狩猟の公共性)
第5章 クマと向き合う(捕獲と威嚇のメッセージ性;規則性と不規則性;ゾーンディフェンスとオフェンシブなアクション;遭遇しないために)
著者等紹介
田口洋美[タグチヒロミ]
1957年、茨城県生まれ。民族文化映像研究所、日本観光文化研究所主任研究員を経て、1990年に「マタギサミット」を主宰。1996年に狩猟文化研究所を設立。2005年、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了、博士(環境学)。同年より東北芸術工科大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
45
読み友さんの感想を読んで。2017年出版、クマをはじめとした現在日本で起こっている野生動物と人間の境界線問題を取り上げた内容で、先見性がある内容だと感じました。同時に、圧倒的に生物学的な研究が不足しているとも感じます。うっかり殺しつくしてしまった前科があるのだから、もう全個体に発信機をつける覚悟で予算をつけ、動物の移動をはじめとした生態を把握してほしい。それを受けて初めて動物たちが「荒らす」必要性を断つための対策が取れるのではないだろうか。他分野にわたる研究者の協力がマストだと思います。2024/03/11
ホークス
44
第一次産業の就業者はこの百年で72%から3%に減り、人の生活域が山林から消えた。逆に大型哺乳類の生息域は江戸時代の状態に戻った。今や山林と市街地は直に接している。人里を縄張りとする犬も、放し飼いの禁止でバリアの機能を失った。クマの出没とイノシシの関係など生態研究もまだ足りない。「シシ荒れ」は江戸時代にもあり、狩猟者の組織化や柵・堀の対策がとられていた。動物と人の境界、自然保護の在り方、人材育成など議論すべき課題は多い。自ら対処するつもりで考えるなら、諍いや苦しみを超えた展望が開けるかもしれない。2019/12/15
アナクマ
40
4章_狩猟の公共性。狩猟と農耕は分かちがたく補い合う相補的な関係。農耕は狩猟に守られ、狩猟は農耕により猟場が得られる。そもそも農耕は人間界と自然界のせめぎ合うエリア「最前線」で営まれる行為なので、動物のアタックは絶えない。排除機能が弱体化すれば、結果は言うまでもない(オランダが絶えず排水する必要があるのと同じだ)。一次産業就業者が5%しかいない日本の野生動物問題が、本質の見えにくい話題で終わりがちなのも仕方ない。◉なお、著者は狩猟文化研究者なのでそちら方面の知見のほうが興味深い(三面の山もらいなど)。→2023/12/02
樋口佳之
38
unlimitedで読む日本のクマなど野生動物の回帰問題。気候変動で生存域が縮小してやせ衰えた北極グマの映像とか見るけども、日本では人口減少も相まってクマ被害の回帰現象があるのかと驚きました。そう言えば最近自宅目の前の電線をつたうハクビシン見たものなあ(23区住です)。幅広い議論がなされていて、困っている方にはおすすめかも2021/04/04
ykshzk(虎猫図案房)
29
もともと大型野生動物の生息地であった平野や丘陵地、盆地を奪って更なる農耕地へと開拓してきたのは人間で、クマやイノシシ達は今、最良の土地を目指してUターンし始めていると著者。明治からの100年は日常的に野生動物に遭遇せず人間が生きてこられた異常な期間だったとも。もちろん木の実の豊凶や温暖化などの原因もあるが、野生動物を山奥に閉じ込めたのも人間なら、今解放しつつあるのも人間。私たちの暮らし方が野生動物の居場所をコントロールしてきた歴史を自覚するべきだと感じた。貴重な経験と知識を持つマタギが減っていくのも残念。2024/07/01
-

- 和書
- 新訳金瓶梅 〈上巻〉
-
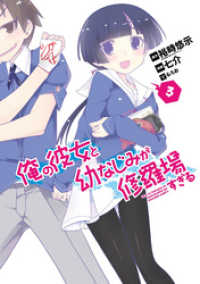
- 電子書籍
- 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる3巻 …