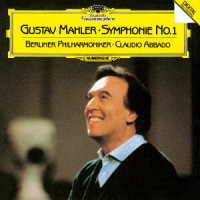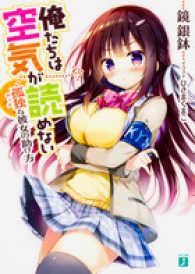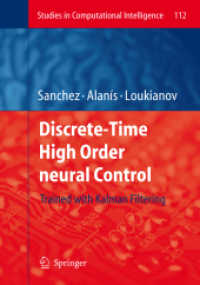内容説明
誰よりも穂高を愛し、穂高に暮らし、仲間とともに多くの遭難者を救助。漫画『岳』の宮川三郎のモデルとなった熱血漢。穂高岳山荘元支配人・宮田八郎の遺稿集。
目次
第1章 穂高に生きる―山小屋暮らし三〇年の日々(一〇代で穂高の小屋番に;はじめて出動した遭難現場;憧れと修業と研鑽の日々 ほか)
第2章 遭難救助の現場から―人を助けるのは当たり前(子供のはずが…予想外の事態の救出劇;スタッフ総出で救助救命に奔走した一夜;奥穂高岳「間違い尾根」のハプニング ほか)
第3章 わが師、わが友―その誇りと英知と死(穂高の守り手たち;映像で描く串田さんの言葉;「アルパインクライマー」という矜持 追悼・今井健司 ほか)
著者等紹介
宮田八郎[ミヤタハチロウ]
1966年4月4日神戸生まれ。学生の頃から穂高を訪れ1991年穂高岳山荘スタッフとなり、1994年~2006年の間、支配人を務める。現場にいる身として遭難救助にも多数出動。小屋番の傍ら、2001年映像制作会社ハチプロダクションを設立、長年にわたり山岳映像を撮り続け、穂高の四季の表情を数多くの作品に残した。2018年4月5日、南伊豆にてシーカヤック中に落命。享年52(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
177
筋力や体力だけでは助けられない世界。視界を遮られる中で危険を顧みず最善の方策を考える。穂高の小屋に身を置いた宮田八郎さんの人生を振り返る本書。山小屋は慌ただしく時に穏やかである。経験の有無を問わず登山者は訪れる。鍛錬された者でさえ一歩踏み誤れば滑落する状況においては厳しさも必要である。命を救われた者が残す言葉は感謝とは限らない。山を畏れ愛さずして務まらないだろう。救助すれば野戦病院となり懸命の処置を行う。お別れの言葉に胸が痛む。人は生まれれば必ず死ぬ。なぜ人は生きるのだろうか。なぜ人は山に登るのだろうか。2025/07/21
けんとまん1007
74
穂高岳山荘に泊まったことがある。新穂高温泉から槍ヶ岳・南岳・大キレットを通り北穂高岳山荘に泊まり、一旦、涸沢におりて登り返すルートで訪れた。戻りは、そこから新穂高温泉へ。ここの描かれている一帯のうち、ある程度は行ったので懐かしさとともに、山小屋の役割、山に関わる人たちの思い・役割も感じ取れるので、納得することが多い。山に相対する時は、何よりも謙虚さが必要だと思っている。それでも、自然の力にはかなわないことが多い。そのことを忘れてはいけない。2023/02/21
サンダーバード@読メ野鳥の会・怪鳥
69
(2024-70)【図書館本】北アルプスの主峰穂高岳で30年にわたって数えきれないほど多くの山岳遭難救助に携わった穂高岳山荘元支配人、宮田八郎氏の遺稿集。多くの登山者が訪れる穂高はなんと年間20人もの人が遭難死しているという。「命懸け」では救助はしない、とは言いながらも山岳救助の第一人者で彼の「師匠」でもある人が救助作業中に落命したりする現実。せめて山を利用する私たちとしては自分の力量に応じて、決して無理な行動はしない事を守り山を楽しみたいと思う。★★★★2024/05/25
獺祭魚の食客@鯨鯢
65
北アルプスで涸沢を拠点として数多くの遭難者を救助してきた伝説の山男の活動記録です。山岳コミック「岳」にもモデルとして登場しました。登山ブームのため中高年の事故が増えていることは当事者の私にも耳の痛い話ですが、山はテレビで視るようにいつも私たちを受け入れてくれる訳ではありません。二年ほど前、錦秋の涸沢カールとモルゲンロートを体験しましたがその時の感動は忘れられません。登山者が安全に登山できるのは、このような方々の命を懸けた活動あればこそであることを忘れてはなりません。宮田さんのご冥福をお祈りします。2020/01/14
goro@the_booby
62
やはり美しい穂高は気の抜けない山なんだなぁ。山に通いなれた人でも登山者とすれ違うほんの一歩で滑落してしまったり、どこで死が待っているのか分からない。宮田さんは小屋番として救助に携わる人として様々な死を見てきたからか本書の言葉が自身の悩みも伺えるけど、芯の通ったメッセージとなって残された。山で死んだらいかんのじゃなくて山では生きなきゃだめだと言うのです。まだまだ伝えたいことがあったと思いますが、穂高の空から見守ってくださいね。合掌。2019/07/06
-

- DVD
- 宮本から君へ